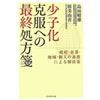ワークライフバランスインタビュー

「ワークライフバランスは生活と仕事の質の相乗効果を図るもの」
第4回
株式会社富士通総研 経済研究所 主任研究員
渥美 由喜さん
『ワークライフバランス』とは
- 高橋:
- ここ数年でやっと日本でも『ワークライフバランス』という言葉が使われるようになってきましたね。
渥美さんは『ワークライフバランス』をどのようなものとして位置付けていらっしゃいますか。 - 渥美:
- 私は、『ワークライフバランス』とは、ワーク(仕事)の根本にライフ(生活)があって、ライフの質が上がると、ワークの質も上がる、『生活と仕事の質の相乗効果を図るもの』であると思います。
かつて日本は、男性は仕事一筋、女性は家で専業主婦という片働きスタイルでした。
しかし20数年前、男性・女性どちらも仕事をする共働き世帯数が片働き世帯の数を上回り始めました。本来であれば、その時点で徐々に共働きスタイルに社会システムをモデルチェンジすべきだったのですが、「失われた10年」(バブル崩壊後1991年-1992年頃から2002年-2003年頃まで)に経営環境が悪すぎて、そのモデルチェンジがうまくいかなかった。そして最近の好景気の兆しをきっかけに、このモデルチェンジを遅ればせながらやろう、ということがワークライフバランスの根底にあります。
「少子化対策だから」という対処療法的なものではなく、日本の社会システムの変化に対する対応だと思います。共働きモデルでは、男性と女性が互いに“ワーク”と“ライフ”両立することを目指さないといけないと思います。
「ワークライフバランス」推進へのアドバイス ~企業編~

- 高橋:
- 全くその通りですね。昇進などに男女の差別が残っている企業もありますし、本当に勿体無いですよね。2005年、次世代育成法(次世代育成支援対策推進法)が施行されてから、『ワークライフバランス』を考え始めた企業様も多くなりました。でも育児休業制度等の制度はあるにも関わらず活動に落とし込めない、といった例が多いようです。なぜでしょうか?
- 渥美:
- 制度と利用のギャップは統計上でも明らかです。従業員へのアンケートによれば、最も多い理由は利用に躊躇してしまう雰囲気があるから、ということです。自分が制度を利用すると周りに迷惑をかけてしまうという遠慮、自分以外が利用することへの不安、こうした理由で活動に落とし込めない。
ですから、まずは従業員の意識改革が必要であると考えられます。
『ワークライフバランス』という言葉の流行に対し、意識が変化するのはこれからです。 - 高橋:
- 渥美さんご自身、従業員の意識改革とワークライフバランスの確立に成功している企業様と接触されていると思うのですが、それらの企業様の取り組みのBefore ⇒ Afterを教えていただけますでしょうか。
- 渥美:
- まず、“Before”は「みんなで仲良く助け合って残業する」。社内の和を保つために残業が無駄に必要されていました。女性の場合は言わずもがな、非常に無理のあるワークスタイルです。男性についてもバランスの取れたワークスタイルに変えなければ、意識改革はできませんし、女性のワークスタイルを改善することもできません。
また、残業には2つの問題があります。ダラダラ残業と、優秀な社員への仕事のしわ寄せです。
これらを解決し、ワークライフバランスを確立する方法は、業務の標準化つまり『仕事の見える化』を行うのです。そして、時間当たりの生産性を測定し、フィードバックしていく。そうすると従業員の間で仕事の質の格差が見えてきます。具体的には、5時から社員、のように生産性の低いダラダラ残業をやめさせ、また優秀な社員へしわ寄せされていた仕事を分散させて負荷を減らすことができ、過労の予防になります。
まとめると“After”では、『仕事の見える化』によって仕事の質を比較でき、評価できる評価軸が出来上がり、業務効率が格段に上がります。
ワークライフバランスの確立を成功させる要素の一つである、『無駄の見直し』が業務効率を上げ、なおかつ業務のしわ寄せが無くなることで、“ワーク”、“ライフ”の両方の面で高い効果を上げていることが分かります。 - 高橋:
- 逆にワークライフバランスへの対策がなされておらず、社内風土に黄色信号が出ている企業はどんな企業なのでしょうか?
- 渥美:
- そもそも女性活用は必要ないとする企業がそれに該当します。例えば、「女性は若い方がいい」「寿退社が当然」というような言葉が経営者から出ているような会社でも、本当は優秀な女性は沢山います。
妊娠・出産・育児期の女性にはどうしても時間制約が生じやすいので、企業としてサポート体制を組み、そこにベアーズさんのような家事代行サービスを導入すればいいと思います。子供を持つことによるワークスタイルの変化という点では、「時間当たりの生産性の向上」というのが重要な視点です。私自身、18時に息子を保育所に迎えにいくときに、保育園の玄関の柵につかまってお迎えを待ちわびている息子の顔を思い浮かべると絶対に遅刻できないというプレッシャーから、16時17時くらいになると業務効率は格段に上がりますね(笑)。人によっては、妊娠・出産・育児期で仕事の時間当たりの生産性は落ちる人もいますが、きちんとしたサポート体制を組むことができれば、逆にモチベーションは上がる人が多いのではないかと思います。企業はそこを正確に理解すべきですね。
50年後、日本の労働人口は約3分の1に減少します。これから労働力需給が逼迫していくのは明らかです。何も対策しなければ「人材確保」ができない企業になってしまうことは明らかです。このような悪循環が始まる前に、企業は女性および子育てしたい男性の軽視を見直さなければなりません。 - 高橋:
- ベアーズの法人会員様の中に、男性社員の方が圧倒的に多い企業様もいらっしゃいます。こういった企業の経営者の方もまた、ベアーズのサービスを人事戦略・経営戦略とされています。
このことについて渥美さんはどう思われますか。 - 渥美:
- 先進企業の経営者の方はワークライフバランスを的確に理解されています。女性が働きやすい環境を創るのに、女性のサポートのみを考えるのはナンセンスです。そもそも男性のワークスタイルを見直さなければ、女性のワークスタイルのサポートにはなりません。男性と女性が互いにワークとライフを両立させなければなりません。次世代育成法でも男性の育児休業取得率を現在の0.5%から、5年後に5%、10年後に10%まで引き上げる目標値を掲げました。男性育児休業取得促進は意識改革の一つのきっかけにすぎません。男性のワークスタイルの見直しをどんどん進めていくべきです。
- 高橋:
- しかし意識や考え方を変えることは制度を作ることより何倍も難しいことだと私は思います。
現在の日本社会において、「ワークライフバランス」に関する根本的な教育は残念ながら欠けているのではないかと私は感じます。また、各企業様はそれに対し、どんな対策をされているのでしょうか。 - 渥美:
- 根本的な考え方を変えるためには、「ライフを重視して、ワークを軽視する」という、シーソーのようなイメージの仕方をやめることから始めなければなりません。でなければ常にワークを軽視するとは何事か、という経営者たちからの批判的な意見が絶えないでしょう。
『ワークライフバランス』は、“ワーク”と“ライフ”の相乗効果ですので、企業がやるべきことはワークの面での評価軸を変えること。今までは残業を前提にした生産性の低い働き方を、時間当たりの生産性という部分に評価軸を切り替えることが重要であると思います。そうすれば意識は変わっていきます。 - 高橋:
- 評価軸を切り替えることがポイントですね。
「ただ頑張っている」ことを評価するのではなくて、成果をきちんと評価するということでしょうか。 - 渥美:
- 私は成果というより、むしろ能力が評価の軸であるべきだと思います。
例えば、自分のビジネスを見直す、消費者の視点を持つ等の能力が、子育てをする期間内で開発されます。成果がなくとも能力が高まるのであれば評価すべきです。そして、基本的にワークライフバランスは従業員のやる気を引き出し、その上で業績をあげていくという考えですから、成果を重視し過ぎるとすると、成果を出していない社員が駄目なやつというレッテル貼りされ、その人がやる気を失いかねない可能性があります。やる気を引き出すためのワークライフバランスの推進で、やる気を失い人が出てしまっては本末転倒です。そういった部分をきちんと補完しないと結果的にうまくワークライフバランスを推進できません。
数値化できない部分をきちんと評価する、という考え方を経営者は持たなければなりません。さもなければワークライフバランスはすごくギスギスした環境を生み出してしまいます。
その問題の解決法として、例えば中小企業では最近、数値化しづらいチームへの貢献の評価をし合う試み、社員同士が「ありがとうカード」を贈り合い、感謝を示し合う方法を導入しています。企業によってはありがとうカードに報奨金を設けています。 - 高橋:
- ベアーズでいうリボン賞ですね。弊社でも毎朝朝礼で良いことをした社員をお互い褒め合っています。