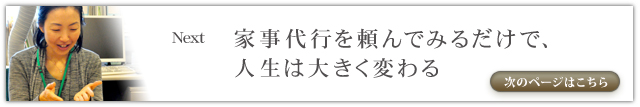ワークライフバランスインタビュー

助け、助けられることで「ありがとう」が循環する社会を創る
第25回
国立保健医療科学院 主任研究員
産婦人科医・医学博士・公衆衛生修士
吉田穂波さん
お母さんにも子どもにも必要な「受援力」を身につけよう
- 高橋:
- 私は最初の子の妊娠・出産時、香港にいたんですよ。香港は、すごく妊婦さんに優しい国なんです。まず、妊娠中に通勤の電車で立ちっぱなしだったことはありません。どんな満員電車でも、乗客みんなが妊婦さんを席に誘導するので、座らせてもらえるんです。赤ちゃんがおなかにいると言わなくても、察してくれます。日本みたいに妊婦マークなんかつけたら、さらにお姫様扱いしてもらえると思いますよ(笑)。
- 吉田:
- そうなんですか!
- 高橋:
 みんなで助け合い、お互い様の精神をもっている。自分が終わったら今度はあなたね、と命のバトンと回覧板を渡しているような感じです。だから、妊婦さんは出産ぎりぎりまで仕事を続けることができるんです。同僚なんて、私が妊娠してから出産するまで毎日、健康にいいスープをつくって持ってきてくれました。今から20年前に社会が子どもを宝として扱うのを目の当たりにし、大きな衝撃を受けましたね。日本もがんばらなきゃ、と。そういう地域社会づくりは、いまだに日本の課題ですよね。
みんなで助け合い、お互い様の精神をもっている。自分が終わったら今度はあなたね、と命のバトンと回覧板を渡しているような感じです。だから、妊婦さんは出産ぎりぎりまで仕事を続けることができるんです。同僚なんて、私が妊娠してから出産するまで毎日、健康にいいスープをつくって持ってきてくれました。今から20年前に社会が子どもを宝として扱うのを目の当たりにし、大きな衝撃を受けましたね。日本もがんばらなきゃ、と。そういう地域社会づくりは、いまだに日本の課題ですよね。- 吉田:
- いやあ、そういう社会を日本にもつくりたいですよね。
- 高橋:
- そこは先生と私の共通のミッションだと思っています。
- 吉田:
- 社会を変える手がかりのひとつとして、支えられる側にも何かできることがあるんじゃないかと思い、「受援力」についてのパンフレットをつくったんですよ。この受援力という言葉は、もともと内閣府が被災地のボランティアを地域で受け入れる環境・知恵などが必要だということで、支援を受ける力のことを指してつくった言葉なんですよね。でも、災害ボランティアの受け入れだけでなく、子育てしているお母さんが周りに助けてもらうきっかけをつくることにもつながると思ったんです。困っている人が助けを求め、助けた人も感謝されてうれしくなる。そんな循環をつくれたらいいと思いました。
- 高橋:
- 受援力、非常に大事な力だと思います。
- 吉田:
- パンフレットには、私がハーバードで学んできた交渉術やアサーティブネス(自分の心を開示し、相手を尊重するコミュニケーションの技法)、アンガー(怒り)マネジメント、リソースマネジメントなどの知識を詰め込んでいます。アサーティブネスと書いてもピンと来ないと思いますので、「気持ちよく頼む技術」というように、ソフトな言い回しに変えて入れています。芯にあるのは、やはりみんなで助け合い、その助け合いが循環して回っていく社会にしたいという気持ちです。
- 高橋:
- すてきですね。
- 吉田:
- 私はこれ、子どもにも必要だと思っているんです。最近、お子さんたちが困っているときも人に頼らないことに気づくことが多いんです。泣きべそをかいている小学生のお子さんに私が「どうしたの?」と声をかけても、泣きそうな顔で「大丈夫です」と言ったり、わーっと泣いて走って行ってしまったりする。子どものうちから、人に頼らないくせがついてしまっているのではないかと感じます。
- 高橋:
- 親御さんが誘拐などの事件を警戒して、他人に警戒心を持つよう教えてるのかもしれませんね。でも本当は、ピュアな心でお互いがお互いのことを受けとめあえるといいですよね。それいう社会をつくっていくのは、すごく難しいことです。大抵の人は、自分一人が思っていても世の中は変えられないと諦めてしまう。でも、大丈夫です。私達みたいにしぶとく諦めない人がいると(笑)、必ずそこから思いは伝播していくと思います。共感する人が現れますよ。
- 吉田:
 そうですよね。女性の幸せや家族の幸せ、子どものためにというところが原点なんですよね。
そうですよね。女性の幸せや家族の幸せ、子どものためにというところが原点なんですよね。- 高橋:
- 順番にいけば、私達のほうが子どもよりも先に天国に招かれていくわけですよね。私達がいなくなっても子どもたちは生きていき、またその子どもたちも生まれてくる。そう考えると、自分の人生は今世で終わらないと強く思います。自分の寿命は、自分がいなくなったその先の世界をつくるためにあるんです。
- 吉田:
- 私も100年後、1000年後のことをいつも考えるようにしています。地域で妊産婦さんを守ろうというプロジェクトも、行政のなかの一事業として組み込んでいただくとか、大学の研修プログラムとして続くとか、私がいなくなっても生き残るようにと思って設計しています。
- 高橋:
- 私は先日、内閣府の男女共同参画会議から家事代行サービスを国として勉強させて欲しいというお声がけをいただいて、うかがってきたんですよ。
- 吉田:
- すばらしい! ベアーズさんのサービス、注目されているんですね。
- 高橋:
- きっとおじさまばかりだと思って気合いを入れて行ったのですが、ふたを開けてみると男性は一人、後は女性の参加者ばかりだったんです。穂波先生の自治体で妊産婦さんを守るプロジェクトも、女性の担当の方が多いのではないですか?
- 吉田:
- そんなことないんです。もともと防災や災害関連の会議となると男性社会なので私一人が女性ということもよくあります。厚労省の会議などでも、やはり男性が多いですね。そこはこれから変えていくべきところだと感じています。でも、家事代行サービスが男女共同参画会議で注目されているというのは、本当に喜ばしいことです。