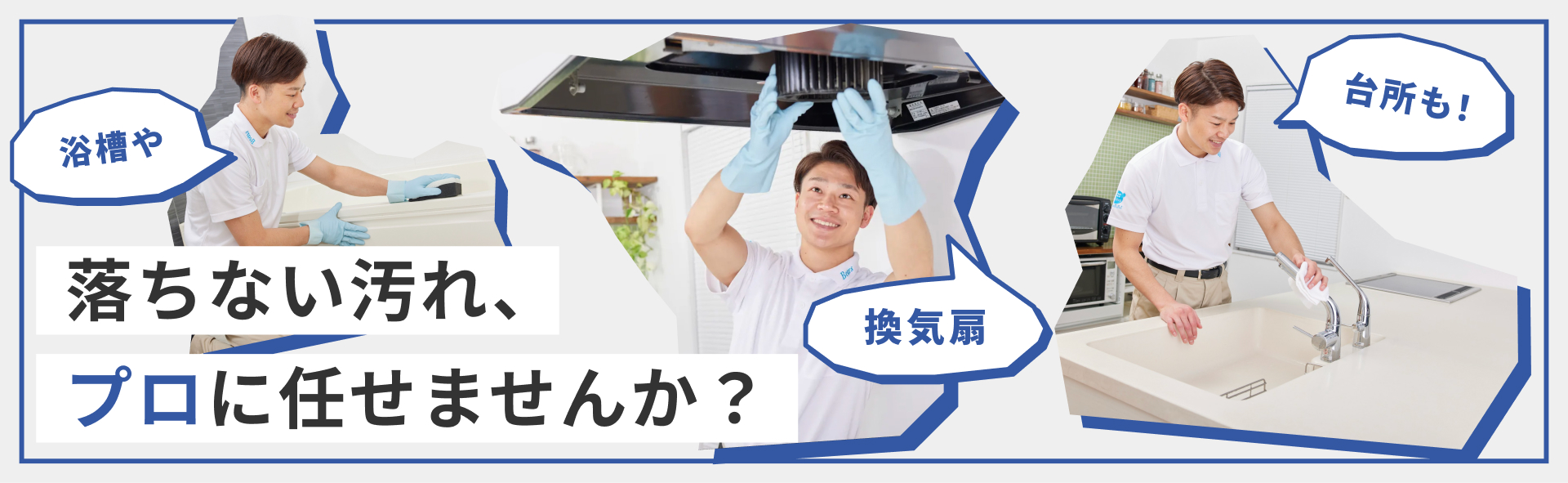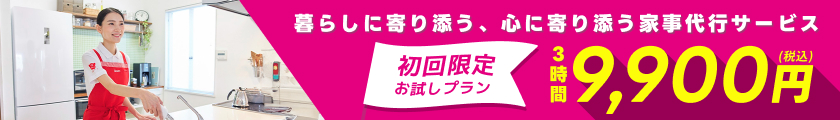大掃除はいつから?年末にやる意味やいつまでに終わらせるべきか解説
家事の悩み
更新日:2024.12.12

この記事を読んで欲しい人
-
忙しくて時短できる暮らし術が知りたい
-
効率的に掃除するためにおすすめの方法を知りたい
-
仕事や子育てと家事の両立が大変で、家事代行が気になっている
年末が近づくと、大掃除をいつから始めて、いつまでに終わらせればいいのか、悩んでしまいますよね。新しい年を気持ちよく迎えるためにも、大掃除は欠かせない行事です。年内に終わらせられるよう、適切なタイミングで始めて、計画的に進めることが大切です。
この記事では、年末の大掃除の由来、大掃除を始めるのにおすすめの時期、避けるべき日にちなど、詳しく説明します。大掃除についての理解を深めて、清々しい新年を迎える準備をしましょう。
目次
年末の大掃除の日とは?意味や由来を解説

年末の大掃除は、大晦日に行うものだと考える方も多いかもしれません。しかし、実際には毎年12月13日が「大掃除の日」とされています。お正月の準備を始めるのに縁起の良い日にちです。この日には、日本の神社やお寺でも煤払いの行事が行われています。
さらに、年末の大掃除は日本に古くから伝わる風習であり、単に家の中をきれいにするためだけのものではありません。新しい年を迎えるための大切な行事として、長年にわたり受け継がれてきたものです。ここでは、年末の大掃除の起源を探っていきます。
・大掃除の由来は「煤払い(すすはらい)」
・年末に大掃除するのはなぜ?煤払いから見る大掃除の意味
それぞれ詳しく、見てみましょう。
大掃除の由来は「煤払い(すすはらい)」
諸説ありますが、大掃除は日本に古くから続く「煤払い(すすはらい)」という行事が由来といわれています。
煤払いの歴史は古く、平安時代の宮廷行事が起源といわれています。当時、宮廷や貴族の屋敷では年末に掃除や清めの儀式を行う習慣がありました。これらは、新しい年に年神様を迎えるための重要な儀式とされていました。実際、平安時代に書写された法典「延喜式」にも、宮中での清掃や年末行事に関する記録が残されています。
室町時代では、寺院や神社などの宗教施設でも煤払いが行われるようになり、さらに江戸時代に入ると12月13日が「正月事始め」とされ、煤払いの行事が一般的となります。
江戸城は徳川幕府の中心地であり、国家的な儀式や行事が行われる場所でした。煤払いは江戸幕府の中でも重要視されていた行事で、新年を迎えるために城内を清め、悪い運気や穢れを祓うために行われていました。
さらに旧暦の12月13日は「鬼宿日」で鬼が外に出歩かない吉日とされていたため、儀式や行事に最適な日と考えられていました。この日、江戸城で行われていた煤払いがきっかけで、庶民の間にも大掃除の習慣が広まったといわれています。
※参照:神社本庁公式サイト「煤払い|おまつりする」、京阪電気鉄道株式会社「第百八十四回 京の煤払(すすはら)い|京都ツウのおすすめ|おでかけナビ」、神童青年全国協議会「知っておきたい豆知識|年中行事と神社」
年末に大掃除するのはなぜ?煤払いから見る大掃除の意味
年末の大掃除には、日本の伝統行事「煤払い」が深く影響しています。煤払いの本来の目的は、新年に幸福をもたらしてくれる年神様をお迎えするためです。年神様を始め、神様は穢れを嫌います。年神様が気持ちよく過ごせるように、煤払いで家屋内をきれいにするのです。
また煤払いにはお清めや、厄払いの意味も込められています。煤や埃と一緒に一年間の厄を落とし、清らかになった家で新しい一年を迎えることは、昔の人にとって重要な行事でした。
現代においても、この煤払いの行事は神社や仏閣で行われています。
煤払いでは笹竹の先に葉や藁を付けた「清め竹」で、社殿に溜まった煤や埃を払って清めます。使用した清め竹は、後日行われる左義長(さぎちょう)や「とんど」などの年明けの行事で、お焚きあげされています。
※参照:神社本庁公式サイト「煤払い|おまつりする」、食卓のお料理を彩る紀文食品「お正月と年神様|大切にしたいお正月の風習」、ヤシロ永代供養ナビ「年神様(としがみさま)」とは?年末は福徳と来訪する、年神様を迎える準備をしよう!」
年末の大掃除はいつから始めるべき?いつまでに終わらせるのが正解?

「年末の大掃除はいつやるのか、わからない」「大掃除してはいけない日ってあるの?」と、疑問を抱えている方も多いでしょう。年末の大掃除を始める具体的な時期に決まりはありませんが、12月13日は縁起が良いとされています。
また大掃除を避けるべき日もあり、12月28日までに終わらせるのが理想的といわれています。これはあくまで縁起を意識したものですが、心身ともに清々しい新年を迎えるために取り入れてみるのも良いかもしれません。
以下では、大掃除におすすめの時期、避けた方が良い時期について解説します。
・大掃除おすすめ時期:12月13日開始、12月28日までに終了
・やってはいけない?年末の大掃除を避けるべき日
それぞれを、詳しく見てみましょう。
大掃除おすすめ時期:12月13日開始、12月28日までに終了
日本の年末の大掃除は、12月13日に始めるのがおすすめです。12月13日は「正月事始め」とされ、この日に煤払いなどの年末準備を始めるのが縁起が良いとされています。年末年始に余裕を持って過ごす意味でも、早めに大掃除に取り掛かるのが良いでしょう。
理想としては、12月13日から始め、12月28日までに終わらせるのが良いとされています。とくに12月28日は、数字の八が末広がりの形をしており、しめ縄などの正月飾りを飾るのに縁起の良い日と考えられています。早めに大掃除を済ませ、12月28日に正月飾りを準備するのが最適です。
早めに大掃除を済ませたいが、忙しくて時間が取れない方は、ぜひベアーズのハウスクリーニングの利用を検討してみてください。
やってはいけない?年末の大掃除を避けるべき日
年末の大掃除は、12月29日、大晦日の12月31日、さらにお正月の1月1日を避けて行うものとされています。年末の大掃除は、日本に古くから伝わる伝統行事「煤払い」が由来です。
煤払いは、年神様を迎える大事な行事と考えられており、縁起が悪い日に行うのは避けるべきと考えられてきました。年末の大掃除を避けるべき日、その理由については次の通りです。
※参照:花・花束を贈るフラワーギフト通販の【日比谷花壇】公式サイト「正月飾りの花の意味は?お正月に飾りたい縁起の良い花」
12月29日
12月29日は、大掃除を避けるべき日にちのひとつです。日本の伝統的な考え方では、「9」は「苦(く)」を連想させるため、不幸や困難を招く縁起が悪い数字とされてきました。とくに29日は「苦(く)」がつく日であり、「二重の苦」「苦松(苦・待つ)」、「苦餅(苦・持ち)」と読めるため、新年を迎える大事な行事には相応しくないと考えられています。
日本の伝統に沿って大掃除を始めるなら、もし、12月28日までに大掃除が終わらなかった場合は、30日に済まし正月飾りを飾ると良いでしょう。
・「二重の苦」・・・字の通り「二重の苦しみ」を連想させる。
・「苦松(苦・待つ)」・・・苦しむ松飾りを連想させるため。新しい新年を迎える日には不適切である。
・「苦餅(苦・持ち)」・・・「苦を持つ」という意味を連想させるため。苦しみや困難を抱え込むことを暗示する。
12月31日(大晦日)
12月31日は「一夜飾り」と呼ばれ、年末に大掃除するのは避けるべき日とされています。一夜飾りとは、正月飾りを31日に飾ることで、急いで準備する様子が葬儀の飾りと重なり、縁起が悪いと考えられています。
正月の準備を急いで済ませるのは、神様に対して失礼とされているのです。また葬儀の飾りは急いで用意される場合が多いため、12月31日に年末の大掃除をするのは、不吉とされています。大晦日やその近くに大掃除をするのが一般的と思われがちですが、実際には縁起の良くない日とされ、避けられてきました。
1月1日(お正月)
大掃除は年が明けてから行う方も、少なくありません。しかし1月1日も、大掃除をしてはいけない日といわれています。その理由は、来てくださった年神様を追い払ってしまうからです。例えば、トイレ、浴室、キッチンなどの水回りの掃除は、神様を洗い流すといった意味合いを持つため、控えたほうが良いでしょう。また、「服を洗い流す」というイメージから、正月には洗濯しない方が良いと考えられています。
※参照:駒澤大学 学術機関リポジトリ「民俗学的に見た年末年始の習俗 和田 謙寿」
年末の大掃除は日本だけ?海外の大掃除事情

大掃除の習慣は世界各国にありますが、年末に行うのは日本特有であり、海外では地域によって大掃除を行う時期が異なります。
欧米では、「スプリングクリーニング」と呼ばれ春に大掃除する習慣があります。この習慣はもともと、冬に使用していた暖房器具から出る煤や灰を掃除することが目的で、春の暖かい時期に行われていました。
現代では、煤や灰が出る暖房器具はほとんど使われていませんが、家の汚れを落としたり衣替えをしたりと、春を迎えるための準備として、この習慣は今も続いています。
また中国や韓国など旧暦を使用している地域では、正月の時期が日本とは異なります。正月を迎えるための大掃除の習慣はありますが、その時期は旧暦に基づいて行われます。
※旧暦は月の満ち欠けと太陽の運行を基準とする暦法で、現在広く使用されているグレゴリオ暦(新暦)とは異なります. 旧暦の1年は約354日で、旧正月は新暦では毎年日付が変わり、通常1月下旬から2月中旬の間に訪れます。
中国では旧暦12月24日頃から春節(旧正月)の準備が始まり、この時期に大掃除を行います. 韓国でも旧正月(ソルラル)に合わせて大掃除などの準備をします。
年末の大掃除をするならスケジュールを立てるべき

長い歴史を持つ年末の大掃除ですが、「忙しくて、なかなか時間が取れない」「毎年、大掃除が間に合わない」と悩んでいる方も多いでしょう。年内に大掃除を済ませるためには、まずはスケジュールを立てるべきです。計画的に進めることで先の見通しが立ち、モチベーションの維持にもつながります。以下では、大掃除のスケジュールの立て方について解説します。
・スケジュールを立てるときのポイント
・大掃除チェックリストを活用する
それぞれを、詳しく見てみましょう。
スケジュールを立てるときのポイント
年末の大掃除のスケジュールを立てるときは、掃除箇所、自分や大掃除する家族の予定、ゴミの収集日をチェックすることから始めましょう。とくに大掃除は、不用品の処分から始めると効率的です。必要なものと不要なものを仕分けた後、可燃物、不燃物、粗大ゴミに分別し、それぞれの収集日に合わせて出しましょう。
自分も含めて、家族のスケジュールは余裕を持って設定するのがおすすめです。急な仕事や予定が入っても、慌てず対応できるようにしましょう。天井や壁といった高い場所、子供部屋など、普段では自分1人でなかなか掃除できなかった掃除場所を家族にお願いするのもひとつの方法です。
また、掃除の基本は「上から下へ」「奥から手前へ」です。大掃除の順番に決まりはありませんが、この基本を意識しながら大掃除のスケジュールを立てると良いでしょう。下から掃除を始めると、あとで上を掃除したときに埃や汚れが下に落ちてしまい、きれいにした部分がまた汚れてしまいます。そのため、掃除は天井や壁などの高いところから始め、最後に床など下に落ちた埃や汚れを取り除けば、無駄な手間をかけず効率よく進められます。
同様の理由で、収納棚やタンスなどは「奥から手前へ」を意識するとスムーズです。ぜひスケジュールを立てる際の、参考にしてください。
大掃除チェックリストを活用する
スケジュールと合わせて、大掃除チェックリストを作成し、活用するのがおすすめです。大掃除チェックリストは、掃除場所ごとに予定日や担当者、完了済みかどうかを書き込めるリストのことを指します。大掃除チェックリストの例は、次の通りです。
| 大掃除チェックリスト | ||||
|---|---|---|---|---|
| 掃除場所 | 掃除順番 | 担当者 | 予定日 | 実施 |
| キッチン | 換気扇 | ママ | 12/1 | ☑ |
| コンロ | ☐ | |||
| シンク | ☐ | |||
| 家電 | ☐ | |||
| 床 | ☐ | |||
| お風呂 | 換気扇 | パパ | ☐ | |
| 排水溝 | ☐ | |||
| 浴槽 | ☐ | |||
| 壁・床 | ☐ | |||
大掃除チェックリストを作成すれば、家族で分担して大掃除をしていても、大掃除全体の進捗状況がひと目で把握できます。とくに大掃除を途中で挫折してしまう方は、しっかり活用しましょう。また事前に掃除場所をリスト化すれば、見逃しがちな場所もしっかり掃除できます。掃除場所を絞ったら、掃除場所ごとにチェックリストを作成しましょう。
年末の大掃除を効率的に進めるコツ

「忙しい年末だからこそ、大掃除は早めに終わらせたい」と考えている方も多いでしょう。年末の大掃除は、むやみやたらに進めると余計に時間がかかってしまう場合があります。先ほども述べた通り、まずは掃除場所を決めて、スケジュールとチェックリストを作成したうえで取り掛かりましょう。
また年末の大掃除を始める際は、事前に掃除道具が揃っているのを確認しましょう。万が一、掃除用洗剤がなくなったり、雑巾が足りなかったりすると、買い物に出る必要があり大掃除に集中できなくなってしまいます。SNSやテレビで話題の掃除道具や洗剤を揃えたくなりますが、大掃除は普段使っているもので十分です。大掃除に集中できるよう、事前に準備しましょう。
以下では、年末の大掃除をより効率的に進めるコツを紹介します。
・まずは不用品を片付ける・整理整頓をする
・ゴミ収集の最終日を確認しておく
・大掃除に便利なアイテムを揃える
・大掃除の順番を工夫する
早めに年末の大掃除を済ませられるよう、それぞれのコツをしっかりチェックしましょう。
まずは不用品を片付ける・整理整頓をする
まずは不用品を処分し、整理整頓したうえで大掃除を始めましょう。部屋に散らばっているものなど、掃除の邪魔になるものを片付けるだけでも部屋がスッキリして見えるものです。さらに掃き掃除や拭き掃除もしやすくなるため、大掃除の効率化につながります。
家族の人数が多いと、洋服や日用品なども多くなりがちです。不用品の仕分けに時間がかかりそうな場合には、11月頃から始めたり、家族で手分けして作業したりすると良いでしょう。
また不用品を片付けるときは、収納しているものを全て取り出してから仕分けるのがおすすめです。不要なものと必要なものを分けた後は、定位置を決めたうえで収納しましょう。
なかには、「必要かどうかがわからない」と悩んでしまうかもしれません。その際は、1年以内に使っているか、必要な時に入手できるか、緊急時に必要なものかをポイントに、必要か不要かを判断すると良いでしょう。子どもの創作物など、なかなか処分できないものは写真として保管するのもひとつの方法です。どうしても処分に迷うときは、保留にし日を改めて仕分けると良いでしょう。
ゴミ収集の最終日を確認しておく
不用品を仕分けた後は、大量のゴミがでます。不用品をスムーズに処理するためにも、ゴミ収集の最終日をしっかり確認しましょう。
ゴミ収集日のスケジュールをチェックしておかないと、家の中にゴミを保管したまま新年を迎えることになってしまいます。とくに粗大ゴミや不燃ゴミは収集回数が少ないため、収集日を逃さないよう注意が必要です。
「ゴミを出し忘れてしまった」「不用品の片付けに手間取って、収集日に間に合わなかった」というケースもあるでしょう。ゴミ収集日に出せなかったゴミは回収業者へ依頼したり、ゴミ集積所に直接搬入したりするのも1つの方法です。ただし、どちらも有料となるため、事前に料金を確認しておきましょう。
年末年始は、ゴミ収集が休みの自治体がほとんどです。また年末は、どの家庭でも大掃除を行っており、回収業者やゴミ集積所も混み合っている可能性が考えられます。そのため、不用品の片付けは早めに行い、余裕をもって処分できるよう、スケジュールを組み立てることが大切です。
大掃除に便利なアイテムを揃える
大掃除を効率よく進めるためにも、便利グッズを揃えておくと良いでしょう。大掃除では壁や天井など、普段はお手入れしない場所もきれいにしておきたいものです。窓や玄関周りなど、さまざまな掃除場所があります。そのため掃除場所に合わせて、以下のような掃除道具や洗剤を買い足しておくのがおすすめです。
| あると便利な掃除アイテムの一例 | |
|---|---|
| 掃除場所 | 掃除アイテム |
| キッチン | 重曹、食器用スポンジ、メラミンスポンジ、新聞紙 |
| トイレ | クエン酸スプレー、フローリングワイパー |
| 浴室 | ゴム手袋、ゴーグル、マスク |
| 洗面台 | クエン酸スプレー、メラミンスポンジ |
| 窓(各部屋) | スクイージー、小型のサッシ用ブラシ、マイクロファイバークロス |
| リビング | マイクロファイバークロス、カーペットクリーナー、フローリングワイパー |
| 天井・壁・電球 | マイクロファイバークロス、フローリングワイパー |
| 玄関 | 玄関マット用クリーナー、アルコールスプレー、新聞紙 |
ただし高い洗剤や、特別な掃除道具を買い揃える必要はありません。例えば、油汚れがひどいキッチンの換気扇やコンロの五徳などは、中性洗剤に浸しておくと汚れが落ちやすいです。浴室の頑固なカビも、カビ取り剤を吹き付けてキッチンペーパーなどでパックすれば落ちやすくなります。ダイソーなどで安く入手できるものを、上手く活用しましょう。
また大掃除に取り掛かる前に、必要な道具が揃っているかチェックしましょう。とくに洗剤や雑巾は、普段より多めに用意しておくのがおすすめです。掃除道具を確認しておかないと、大掃除の途中で買い足す羽目になり、余計に時間がかかってしまいます。なるべくスケジュール通りに大掃除を進めるためにも、よく使うアイテムは事前にストックしておきましょう。
| 基本の掃除アイテム(一例) | |
|---|---|
| 掃除アイテム | 用途 |
| 雑巾 | 窓や床、家具などの水拭き、乾拭き |
| スポンジ | キッチンや浴室など、こびりついた汚れ落とし |
| モップ | 床掃除(水拭きや乾拭き) |
| 掃除機 | カーペットやフローリングのゴミ・ホコリの吸い取り |
| ゴム手袋 | 手の保護 |
| 使い古しの歯ブラシ | 細かい部分の汚れ落とし(排水口や隙間など) |
| バケツ | 拭き掃除 |
| 洗剤類(住居用洗剤、カビ取り剤など) | 汚れや掃除場所に応じた洗剤で掃除 |
大掃除の順番を工夫する
年末の大掃除を効率よく進めるためには、大掃除の順番を工夫するのも重要なポイントです。とくにキッチン、浴室、トイレなどの水まわりの掃除には、洗剤やカビ取り剤をなじませる放置系掃除が適しています。
放置系掃除では、洗剤をなじませるのに30分〜1時間程度の放置時間が発生します。放置系の掃除を後回しにすると、夜遅くまで大掃除が終わらない可能性があります。そのため水まわりの掃除は午前中など早い段階で洗剤を浸透させておき、その放置時間を活用して他の場所を掃除するのがおすすめです。大掃除のスケジュールを立てる際は、放置系掃除の放置時間も考慮しましょう。
「大掃除を効率よく進めて、1日で終わらせたい」と思う方も多いでしょう。その場合、完璧を目指すのではなく、掃除する場所を絞るのがおすすめです。たとえば、汚れが溜まりやすいリビング、キッチン、トイレ、浴室、玄関の5箇所に集中して掃除すれば、家全体がすっきりしたように見えます。とくに玄関は、幸運の入り口ともいわれており、普段からきれいにしておきたい大切な場所です。大掃除が終わったら玄関にしめ縄を飾り、年神様を迎える準備を整えましょう。
忙しい年末・大掃除に手が回らない場合はプロに頼むのもおすすめ

「年末は忙しくて、大掃除する時間がない」「1人で大掃除するのはめんどう」「自力では落ちない汚れがある」など、年末の大掃除に悩みを抱えている方は、プロに頼むのがおすすめです。
プロに任せれば、大掃除に割かれていた時間も自由に使えます。時間に余裕ができれば、年内に終わらせておきたい仕事や予定に取り組んだり、家族と過ごしたりするのも可能です。
さらにハウスクリーニングのスタッフは、掃除に関する知識が豊富です。家庭用の洗剤や掃除道具では落ちない汚れ、エアコンや換気扇など自力での掃除が難しい場所も、ピカピカに仕上げてくれます。
プロへ大掃除を依頼するとお金はかかりますが、そのコストに見合うだけのメリットがあります。ぜひ年末の大掃除をプロに任せて、気持ちよく新年を迎えてみてはいかがでしょうか。
掃除のプロ「ベアーズ」のハウスクリーニングについて詳しく見る
大掃除ならベアーズのハウスクリーニングにお任せください

年末の大掃除をプロに依頼するなら、ぜひベアーズのハウスクリーニングにお任せください。ベアーズは、20年以上の実績と250万件以上の利用実績を誇る家事代行・ハウスクリーニングサービスを提供しています。
プロのスタッフが汚れの種類や状態に応じて、適切な洗剤や機材を使い、徹底的に清掃します。ベアーズのスタッフは、お客様への対応やマナーも研修でしっかりと学んでいるため、安心してサービスを利用できます。サービス終了後30分以内のフォローコールや手直し保証もついており、ハウスクリーニングが初めての方でも安心して利用できるのが魅力です。
さらにベアーズのハウスクリーニングには家全体の掃除以外にも、さまざまなプランを用意しています。たとえば、「水まわりまるごとパック」は、キッチン、浴室、トイレなどの水まわりだけを重点的に掃除してもらえるプランです。
自分で掃除できる場所は自力で行い、面倒な水まわりはプロにお任せすれば、効率よく大掃除を進められます。苦手な場所や、手間がかかる場所だけプロに依頼するなど工夫しながら、大掃除を早めに済ませてしまいましょう。
大掃除に関するよくある質問

ここでは、年末の大掃除に関するよくある質問をまとめています。
・年末大掃除を業者に依頼するベストな時期とは?
・風水的に大掃除はいつまでに終わらせるべき?
・大掃除で運気アップ・開運効果が期待できる箇所は?
それぞれ、詳しく見てみましょう。
年末大掃除を業者に依頼するベストな時期とは?
年末大掃除を業者に依頼する際は、9〜11月中に予約するのがおすすめです。年末の大掃除シーズンになると、どの業者も予約で埋まってしまい、希望の日時で予約できない可能性があります。
とくに12月の土日祝日は、すぐに予約で埋まってしまう可能性が高いです。そのため、早めにスケジュールを組み、余裕をもって業者に予約すると良いでしょう。どうしても希望の日時に予約が取れない場合は、12月を避けて10月や11月に予約するのもひとつの方法です。あくまで自分や家族の都合を優先し、無理せず大掃除を進めましょう。
また9〜11月になると、ハウスクリーニングを特別価格で利用できるキャンペーンを実施する業者もあります。「ベアーズ」では、年末大掃除キャンペーンを実施しています。キャンペーンの申し込み期間は2024年10月1日〜11月28日まで、サービス提供期間は同年10月5日~12月13日までです。業者によって、キャンペーンの内容や対象期間は異なります。お得に業者に依頼したい方は、ぜひチェックしてみてください。
風水的に大掃除はいつまでに終わらせるべき?
風水では、大掃除は11月から始めて、冬至までに終えるのが理想とされています。冬至は一年で最も昼が短く夜が長い日で、毎年12月22日頃に訪れます。風水では冬至を運気の転換点として重要視しており、冬至までに大掃除を済ませることで、良い運気が家に入ってくると考えられています。
また、風水的には冬至に大掃除を行うのは避けるべきとされています。冬至は、運気が切り替わる重要な日です。この日に掃除すると、溜まった良い運気を外に出してしまうと考えられています。
※参照:ダイヤモンド・オンライン「【神様は見ている】運がいい人、お金持ちの人が、22日冬至にする最強のこと|旬のカレンダー」
大掃除で運気アップ・開運効果が期待できる箇所は?
気の流れを重視する風水では、掃除は開運に効果的とされています。汚れや不要なものが溜まった家は運気が停滞し、悪い気を溜め込みやすいと考えられています。運気の流れを良くするためにも、玄関、トイレ、キッチンの掃除が重要です。
玄関は、運気が入る大切な場所です。玄関が汚れていたり、散らかっていたりすると、良い運気が入りにくくなります。逆に悪い運気を引き寄せる場合もあるため、日頃から清潔で整理された状態にしておくことが重要です。靴の出しっぱなし、ほこりや泥が溜まっている状態では、良い運気は流れ込みません。掃除し、整理整頓してきれいな状態を保てば、全体運アップに効果的とされています。
風水では、トイレは「陰」の気が溜まる不浄の場所であり、汚れたまま放置していると悪い気が溜まり、健康運や金運が下がるといわれています。汚れや悪臭を取り除き、悪い気が溜まらないよう、清潔を保つことが大切です。また風水において、雑誌や新聞紙などの紙類をトイレに持ち込むのは避けるべきとされています。紙が悪い運気を吸い込んでしまうため、置かないようにしましょう。
食べ物を扱うキッチンは、金運や家族運に影響を与える場所といわれています。食べ物や料理を通じて、家族の活力や豊かさを育む場所であるため、しっかり掃除して清潔にしておきましょう。なかでもコンロ周りは、重点的に掃除しておきたい場所です。火のエネルギーが安定すると、金運が上昇するといわれています。コンロにこびりついた油汚れや、焦げ付きなど、きれいに取り除きましょう。
まとめ

年末の大掃除は、12月13日から始め、28日までに終わらせるのが理想です。正月飾りのしめ縄や門松は、28日に飾ると縁起が良いとされていますが、29日は「苦(く)」を連想させるため避けた方が良い日とされています。また、12月31日や1月1日に大掃除をするのも縁起が悪いとされています。
風水では、11月から始め、12月22日頃の冬至までに大掃除を済ませると運気が上がるとされています。いずれにせよ、早めに始めて余裕を持って終わらせることが重要です。
年末の大掃除は、日本に古くから伝わる「煤払い」に由来します。これは、お正月に年神様を迎えるための準備で、厄払いとお清めの意味があります。江戸時代からは12月13日が煤払いの日となり、現在も多くの寺社で行われています。
忙しい現代では、計画的に進めるために、スケジュールやチェックリストの作成が効果的です。時間が取れない場合はプロに頼むのも良いでしょう。この記事を参考に早めに大掃除を終え、気持ちよく新年を迎えてください。
 Related
-関連記事-
Related
-関連記事-
-

ベアーズの料理代行体験プランを使ってみた正直レビュー|在宅育児がぐっとラクに
ベアーズの料理代行体験プランを、在宅で9ヶ月の子どもを見ながら実際に利用。初回限定プランの内容や当日
ベアーズの料理代行体験プランを、在宅で9ヶ月の子どもを見なが
2026.01.20
-

【体験レビュー】冬休み初日にベアーズのベビーシッター体験プランを使ってみた
ベアーズのベビーシッター体験プランを、業務委託パートナーの筆者が実際に利用。冬休み初日に年少(4歳)
ベアーズのベビーシッター体験プランを、業務委託パートナーの筆
2025.12.29
-

【体験レビュー】おそうじ美人GREENで母へ贈る、エアコンクリーニング体験
家事代行のベアーズが提供するハウスクリーニングギフト「おそうじ美人GREEN」。母へのプレゼントとし
家事代行のベアーズが提供するハウスクリーニングギフト「おそう
2025.10.31
-

【体験レビュー】おそうじ美人RED母の日や妻・義母への感謝を伝える体験型ギフトとは?
「おそうじ美人RED」はベアーズの家事代行ギフト。掃除・洗濯・料理など3時間プロに任せられる体験型プ
「おそうじ美人RED」はベアーズの家事代行ギフト。掃除・洗濯
2025.09.03
-

エアコンクリーニングは効果絶大!メリットや業者選びのポイントを解説
「エアコンクリーニングは必要?どんな効果があるの?」 このような疑問にお答えする記事です。 ...
「エアコンクリーニングは必要?どんな効果があるの?」 この...
2025.06.06
-

【産後の家事代行体験記】二児育児スタートの日に頼ったら大正解だった話
産後の心身の負担を少しでも軽くするために、家事代行と育児サポートを活用してみた30代ママの体験記。産
産後の心身の負担を少しでも軽くするために、家事代行と育児サポ
2025.05.03
![]() Pick Up
-ピックアップ-
Pick Up
-ピックアップ-
-

【体験談】ベアーズの家事代行初回お試しプランは、快適な暮らしへの第一歩
ベアーズの「家事代行初回お試しプラン」の体験談をHさんにインタビュー。共働きで1歳の娘を育てるHさん
ベアーズの「家事代行初回お試しプラン」の体験談をHさんにイン
2023.01.19
-

福利厚生の事例8選|従業員の満足度が高いユニークな福利厚生とは
企業が活動するにあたり、従業員は最も重要な財産といえます。優秀な人材が長く働きやすい環境を築くため...
企業が活動するにあたり、従業員は最も重要な財産といえます。...
2022.12.22
-

冷房の使い始めに注意!エアコン掃除や試運転がポイント!【クリーニングサービス体験談も】
夏への準備、エアコンは試運転した方がいいって本当? 季節は5月。夏はまだ先のこと……と思って...
夏への準備、エアコンは試運転した方がいいって本当? ...
2022.05.09
-

【体験談】子どもと過ごせる時間が増えた!家事代行は自分を大切にするためのサービス
こんにちは、家事代行のベアーズです。 共働き夫婦の中には、「仕事と育児で忙しくて家事まで手が...
こんにちは、家事代行のベアーズです。 共働き夫婦の中...
2022.02.10
-

【体験談】家事代行を頼んで時間と心にゆとりができた!帰宅の瞬間が癒しに
こんにちは、家事代行のベアーズです。 オフィスで働くOさん。ご夫婦で共働き...
こんにちは、家事代行のベアーズです。 ...
2022.01.31
-

ウェルビーイングに貢献する福利厚生とは?社員の生産性を高める5つの例
近年、働く上でのウェルビーイング(幸福感や満足感)の重要性が注目されるようになってきました。従業...
近年、働く上でのウェルビーイング(幸福感や満足感)の重要...
2022.01.07