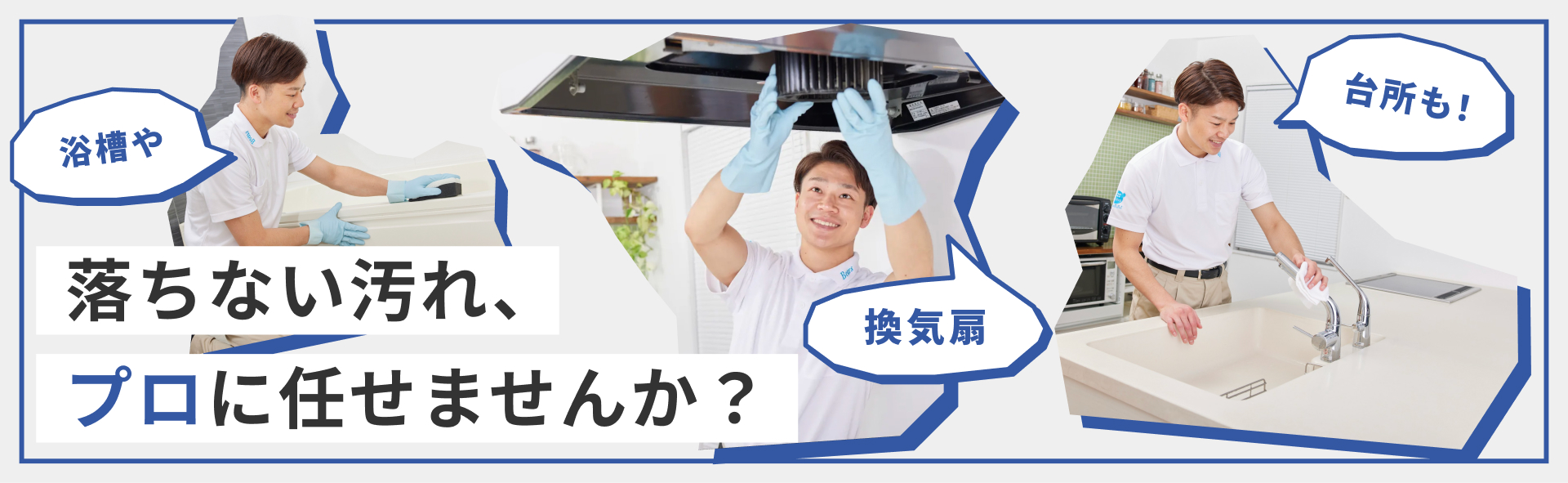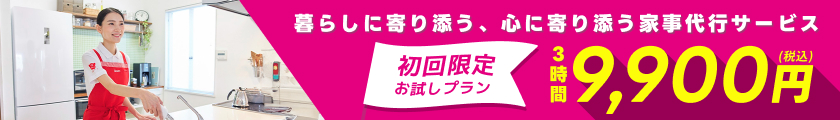大掃除の順番や効率よくやるコツ!おすすめのやり方を徹底解説
家事の悩み
更新日:2024.12.12

この記事を読んで欲しい人
-
忙しくて時短できる暮らし術が知りたい
-
効率的に掃除するためにおすすめの方法を知りたい
-
仕事や子育てと家事の両立が大変で、家事代行が気になっている
年末に行う大掃除は、多くの人にとって悩みの種です。「年末の大掃除は、どこからやる?」「年末の大掃除の仕方がわからない」と、頭を抱えている方も多いでしょう。スムーズに進めるために大掃除を何からするか、やる順番を事前に計画を立てる家庭もありますが、できるだけ時間や労力を減らしたいと考えるものです。
今回は、大掃除を効率よく進めるためのポイント・計画の立て方・おすすめの掃除の順番について詳しく解説します。年末に向けた大掃除の準備に、ぜひお役立てください。
目次
大掃除を効率よくやるために意識すべきこと

まずは、大掃除を効率よく進めるために意識すべきことをチェックしましょう。ポイントは、以下の5つです。
・完璧を求めすぎない
・何年も使用していない物は基本的に処分する
・「上から下へ」を意識して大掃除する
・事前に大掃除の計画・スケジュールを立てる
・大掃除のチェックリストを活用する
それぞれ、詳しく見てみましょう。
完璧を求めすぎない
大掃除を効率よく進めるためには、完璧を追い求めず、自分に無理のない範囲で進めることが大切です。
大掃除で完璧を目指すと、その分時間や手間がかかり、途中で疲れてしまう可能性があります。リビングやキッチン、洗面所、トイレ、浴室など、掃除する場所が多く、細かい汚れまで落とそうとすると体力も気力も消耗してしまいます。完璧を目指すのではなく、7割〜8割程度できていれば十分だと考えるようにしましょう。
また本格的に大掃除しようと、テレビや、SNSなどで話題の掃除用具を揃えたくなるかもしれませんが、購入するための時間やお金がかかってしまいます。大掃除は普段使っている洗剤や掃除道具で十分対応できるほか、さらに時間や費用の節約にもつながります。
大掃除にあまり時間をかけたくない場合は、「これだけは、やっておきたい」と思う掃除を行うなど、あまり力を入れすぎないことが重要です。
何年も使用していない物は基本的に処分する
「大掃除は、どこからやればいい?」「何から手をつけるのか、わからない」と、悩んでいる方も多いでしょう。大掃除する際は、まずは使わないものを確認し、長い間使っていない物は思い切って処分しましょう。
何年も同じ家に住んでいたり、同居する家族の人数が多かったりすると、家電製品や食器類、サイズアウトした衣類など使わない物が増えるものです。不用品を処分するだけでも、部屋がすっきり片付いたように見えます。さらに掃除機や拭き掃除がしやすくなり、大掃除の時間節約にもつながるでしょう。
まだ使える家電製品やダイエットグッズなど、捨てるのがもったいないと感じる物もあるかもしれません。しかし何年も使っていない物は、今後も使う可能性は極めて低いといえます。どうしても処分するのが惜しい場合は、リサイクルショップやフリマアプリを利用すれば、無駄にしたという罪悪感を軽減できるでしょう。
お子さまの制作物や手紙など、思い出の品が収納スペースを占領しているご家庭も多いでしょう。使わないからといって無理に捨てる必要はありませんが、思い出の品を写真に残してから処分するという方法もあります。
ただし不用品を処分する際は、住んでいる地域の自治体の指示に従うようにしましょう。とくに家電製品やバッテリー類は、自治体ごとに処分方法が異なる場合が多いため、事前に確認することが重要です。
「上から下へ」を意識して大掃除する
大掃除に限らず、掃除をする際は「上から下へ」を意識することが大切です。ホコリは上から下へ落ちるため下の部分から掃除を始めると、高い場所を掃除した際にホコリが落ちてしまい、再度掃除をする手間がかかってしまいます。
例えば、床を掃除した後に天井のホコリ取りをすると、ホコリが下に落ちてしまうため、再度床を掃除しなければならず、余計に時間がかかってしまいます。
また同様の理由で、収納棚やタンス周りを掃除する際も「奥から手前へ」が基本です。手前をきれいに掃除しても、奥にあるゴミや汚れを取る際に手前が再び汚れてしまい、結果として二度手間になってしまいます。とくに拭き掃除や掃き掃除を行う際は、上から下へ・奥から手前への順番でホコリや細かいゴミなどを取り除きましょう。
事前に大掃除の計画・スケジュールを立てる
効率よく大掃除を進めるためにも、事前に大掃除の計画・スケジュールを立てましょう。とくに、時間がかかりやすい「放置系掃除」を考慮する点がもっとも大切です。放置系掃除とは、洗剤や洗浄液のつけ置きで汚れを取り除く掃除方法を指します。
放置系掃除が必要な場所は、キッチンの換気扇やエアコンのフィルター、カビが発生しやすい浴室などがあります。放置系掃除は油汚れやカビなど、拭き掃除だけでは落ちない汚れに効果を発揮します。30分〜1時間程、洗剤をなじませておけば、これらの汚れを効率よく落とせます。
大掃除の際に、放置系掃除を後回しにすると、洗剤をなじませるのに時間がかかり、全体の掃除が遅くなってしまいます。そこで放置系掃除が必要な場所をあらかじめ確認し、午前中の早い段階で洗剤をなじませておくのがおすすめです。その間に他の場所を掃除すれば、より効率的に大掃除を進められます。放置系掃除の場所と、それにかかる時間を考えたうえで計画を立てることを意識しましょう。
以下は、大掃除をする日のスケジュール表の例です。掃除時間、所要時間、掃除場所、放置系掃除をするなどのポイントを書き込みます。
| 時刻 | 所要時間 | 場所 | やること |
|---|---|---|---|
| AM8:00~ | 60分 | キッチン | ・換気扇のパーツを外し、洗浄液に浸す ・コンロの五徳などのパーツを外し洗浄液につける |
| AM9:00~ | 60分 | 浴室 | ・排水溝のゴミを取り除く ・カビ取り剤をスプレーしてサランラップでパックする |
| AM10:00~ | 30分 | トイレ | ・便器に洗浄液をなじませる |
| AM10:30~ | 90分 | キッチン | ・換気扇の中を拭き掃除する ・洗浄液につけていた換気扇のパーツをを擦り洗いする ・コンロ周りのゴミを取り除く ・洗浄液につけていたパーツを擦り洗いし戻す |
| PM12:00~ | 休憩 | ||
大掃除のチェックリストを活用する
大掃除のやる気を保つために、大掃除のスケジュールに加えて、大掃除のチェックリストを作成しましょう。スケジュールでは掃除の順番を整理し、一方でチェックリストでは各エリアごとに掃除する場所、予定日と実施日、担当者を設定します。以下に、参考となるお掃除リストの例を載せていますので、ぜひ参考にしてください。
| エリア | 掃除場所 | 担当者 | 予定日 | 実施日 |
|---|---|---|---|---|
| キッチン | 換気扇 | ママ | 12/1 | 12/1 |
| 壁・床 | ||||
| コンロ | ||||
| シンク | ||||
| 家電 | ||||
| お風呂 | 換気扇 | パパ | 12/1 | 12/1 |
| 壁・床 | ||||
| 排水溝 | ||||
| 浴槽 |
例えば、家族で役割を分担してリビングを大掃除すると仮定します。この場合、掃除エリアはリビング、掃除する場所は照明、テレビ・テレビボード、収納棚、床、壁、窓と決めます。担当者の都合に合わせて予定日を記入し、掃除が完了したら各掃除場所にチェックを入れます。
このようにチェックリストを作成して活用すれば、大掃除の進捗状況が一目で分かり、モチベーションの維持につながるでしょう。また家族で分担して大掃除を進めても、全体の進捗を把握しやすく、どの掃除場所が完了しているかも簡単に確認できます。
掃除場所を決めるコツは、掃除の効果が目に見えてわかる場所や、整理するとすっきりする場所を優先することです。先ほども述べた通り、完璧を目指そうとすると体力も気力も尽きてしまいます。またチェックリストのチェック項目が増え、なかなか終わらないと感じ、途中で挫折してしまう可能性が高いです。大掃除を効率化するためには、まずは掃除場所を絞り込んだうえでチェックリストを作成し、それを上手く活用するのが重要なポイントです。
大掃除はどこから始めるべき?おすすめの順番・効率のいいやり方

「年末の大掃除は、どこから始めればいいのかわからない」「何を最初にやるべきか迷う」という方も多いでしょう。大掃除を始める順番に決まりはありませんが、基本的には奥の部屋から始め、最後に玄関を掃除するのが良いとされています。
またキッチンや浴室などの水回りは、放置系掃除が必要となり時間がかかるため、早めに取り掛かるのがおすすめです。掃除する時間がなかなか取れないという方は、別日に少しずつ進めると良いでしょう。以下では、大掃除のおすすめの順番、効率よく進める方法について解説します。
①まずは物の片付けをする
②天井・電球・壁・家具・カーテンレール・窓枠等のホコリや汚れを落とす
③掃除機をかける
④キッチンの換気扇(レンジフード)に洗剤をなじませる
⑤お風呂・浴室のカビにカビ取り剤をスプレーする
⑥トイレの便器内に洗剤をなじませる
⑦窓・網戸の掃除をする
⑧キッチンの掃除をする
⑨お風呂・浴室の掃除をする
⑩トイレの掃除をする
⑪洗面所・洗濯機の掃除をする
⑫リビング・寝室・各部屋の床や棚などを拭き掃除する
⑬玄関の掃除をする
⑭ベランダの掃除をする
なお自宅の間取りや状況に合わせて順番を変えたり、項目を省いたりしても問題ありません。また一人暮らしの年末掃除は、部屋数が少ないため掃除場所が少ないかもしれません。ただし大掃除を無理なく進められるよう、スケジュールをしっかり立てることが大切です。それぞれ、詳しく見てみましょう。
①まずは物の片付けをする
大掃除を始める前に、まずは不用品の処分や必要な物を整理するなど、物の片付けをしましょう。物の片付けをする際は、始めに使う物と使わない物、なかなか判断がつかない保留の物を分別します。分別する際は、場所ごとに一度全部取り出してから始めるのがおすすめです。収納場所のスペースをチェックできるほか、どれだけ物があるかもひと目でわかるため、後から物の収納場所を決める際に役立ちます。
次に、使うと判断した物の定位置を決めましょう。この時、やみくもに決めるのではなく、使う時に「取り出しやすく戻しやすい」場所を意識しながら決めることが重要です。使わない物には、家電製品、衣類、雑誌などさまざまな物が含まれるはずです。各自治体でごみの収集日や処分方法が異なるため、事前に確認して正しく処分するようにしましょう。
保留にした物は保留期間を決めて、別の日に分別すると良いでしょう。どうしても必要か不要か判断できない場合は、以下の基準にそって分別するのがおすすめです。大掃除の始め方がわからないという方は、まずは不用品の処分から始めましょう。
・緊急時に必要な物、人から借りた物、重要な書類は保管する
・後から入手できる物は処分する
②天井・電球・壁・家具・カーテンレール・窓枠等のホコリや汚れを落とす
先ほど述べた通り、掃除の基本は「上から下へ」です。まず天井から始め、徐々に下の方に向かってホコリや汚れを落としていきます。普段の掃除では手が届きにくい天井や電球などには、ホコリや汚れがたくさん溜まっています。大掃除の際には必ずマスクを着用し、ホコリを吸い込まないように注意しましょう。
また家具や家電の隙間や、下の部分は「奥から手前」にホコリや汚れを掻き出すように掃除しましょう。部屋の掃除の順番も同様に「奥から手前」が基本です。奥の部屋からホコリや汚れを集め、最後に玄関から外へ掃き出しましょう。
この順番を逆にしてしまうと、例えば下の部分を先に掃除しても、上を掃除したときに再び汚れてしまい、無駄な手間がかかります。同様に、手前から奥へ掃除すると、せっかく集めたホコリや汚れを外に出せなくなり、非効率です。「上から下へ、奥から手前」を意識して、大掃除を効率よく進めましょう。
③掃除機をかける
奥の部屋から順にホコリや汚れを取り除いた後、掃除機をかけましょう。この際、掃除機をかける順番も奥の部屋から始めるのが効果的です。掃除機をかける際に注意すべき点は、必ず窓を閉めることです。窓を開けると、床に落ちたホコリやダニなどの汚れが風で舞い上がり、掃除機で十分に吸い取れなくなる可能性があります。
さらに、ホコリやダニは非常に微細なため、一度舞い上がると、完全に下に落ちるまでに約8〜10時間かかるとされています。そのため、掃除機をかける際には窓を閉めたままにしておくことが大切です。
④キッチンの換気扇(レンジフード)に洗剤をなじませる
キッチン周りは、先述した放置系掃除が必要な場所やパーツが多いです。なるべく午前中の早い時間帯に、キッチンの換気扇やフィルター、ガスコンロの五徳など、油汚れが酷い箇所に洗剤をなじませておくとスムーズに進みます。なお換気扇の掃除をする際は、必ず電源が切れていることを確認してから作業しましょう。
キッチン周りの掃除は、作業スペースを確保するためにも事前に整理しておきましょう。取り外したパーツのホコリや汚れが飛び散らないよう、作業スペースとガスコンロの上に新聞紙を敷きます。取り外したパーツは、キッチンの掃除用洗剤、またはアルカリ性の重曹を溶かしたお湯に1時間〜2時間ほどつけ置きします。放置している間は、他の場所の掃除を進めると効率的です。
⑤お風呂・浴室のカビにカビ取り剤をスプレーする
お風呂や浴室のカビには、カビ取り剤をスプレーしましょう。とくに頑固なカビは簡単には取れないため、放置系掃除が効果的です。カビ取り剤をスプレーし、放置した後にブラシでこすると、きれいに落とせます。
カビが落ちにくい箇所、例えば浴槽、床、ドアのゴムパッキンなどは、カビ取り剤をスプレーした後、サランラップやキッチンペーパーでパックすると効果的です。洗剤が流れにくく、しっかり浸透するため、しつこいカビも落ちやすくなります。
また天井や壁など高い場所のカビを掃除する際、直接スプレーすると液だれして目や顔にかかる危険があります。高い場所を掃除する際は、フローリングワイパーを使用するのがおすすめです。ワイパーにドライシートを取り付けてカビ取り剤をスプレーし、高い箇所を安全に掃除しましょう。
カビ取り剤を使用する前に、次の3つの準備が必要です。
・換気を行う
・ゴム手袋、マスク、ゴーグルを着用する
・浴室の水分を拭き取ってからカビ取り剤を使う
カビ取り剤を使う際の重要な注意点として、塩素系と酸素系のカビ取り剤を混ぜないことです。これらを混ぜると有毒な塩素ガスが発生し、健康に危険を及ぼす可能性があります。とくに「混ぜるな危険」と表示された洗剤は、取り扱いに細心の注意を払いましょう。カビ取り剤を長時間放置しないことや、浴室の素材にカビ取り剤が使用できるか確認することも大切です。必ず注意書きを読み、正しく使用しましょう。
⑥トイレの便器内に洗剤をなじませる
トイレの便器の黄ばみや尿石などの頑固な汚れには、洗剤をしっかりなじませましょう。サンポールなどの酸性洗剤を便器にかけ、30分から1時間ほど放置してから水で流します。汚れが残っている場合は、トイレブラシでこすって落としましょう。便器内の水を事前に抜いておくと、洗剤が薄まらず効果的です。掃除が終わったら、置き型洗剤を設置すると、清潔な状態を長く保てます。
ただし、酸性洗剤と塩素系洗剤が混ざると有毒な塩素ガスが発生するため、注意が必要です。「混ぜるな危険」と表示された洗剤は、取り扱いに十分注意しましょう。また洗剤を長時間放置すると、トイレの部品が錆びたり、劣化や破損の原因につながる可能性があります。使用方法を守り、洗剤が残らないようしっかりと洗い流すことが大切です。
⑦窓・網戸の掃除をする
放置タイプの洗剤を使用した掃除では、洗剤をなじませて放置している間に、窓や網戸の掃除を進めると効率的です。窓ガラスの汚れは、内側も外側も多くの場合、洗剤を使わず水だけで落とせます。水で濡らした後、スクイージーで汚れを含んだ水を取り除き、最後に拭き上げるだけでOKです。
窓掃除は、まずサッシから始めるのがポイントです。サッシには乾いた砂やほこりがたまりやすく、これが水分を含むと泥状になって落としにくくなります。ハケで汚れを取り除き、掃除機で吸い取った後に、網戸の掃除に取りかかりましょう。
網戸は、掃除機やブラシを使って砂やほこりを取り除きます。その後、水で濡らして固く絞ったぞうきんで水拭きしてください。この時、強く力を入れすぎると網戸が変形したり、破れたりする可能性があるので、慎重に行いましょう。
外側の窓掃除では、まずハケで窓全体の砂やほこりを取り除きます。その後、水で濡らして軽く絞った雑巾で窓を拭き、スクイージーを使って上から下へ水分と汚れを取り除きます。仕上げに、マイクロファイバークロスなどで乾拭きをすれば完了です。
内側の窓を掃除する際は、まず鍵の周辺を中性洗剤を含ませたスポンジでこすり、次に水拭きと乾拭きを行います。その後、窓全体を温かいお湯で濡らした雑巾で拭き、スクイージーで水分を除去して、最後に乾拭きして仕上げます。内側は皮脂汚れが付きやすいため、水よりもお湯を使うと効果的です。
⑧キッチンの掃除をする
キッチンの大掃除も「上から下」の順序で進めると効率的です。まずは換気扇、次に冷蔵庫や電子レンジなどのキッチン周り、その後コンロやシンク下、最後に床を掃除すると良いでしょう。
最初に換気扇の内部を掃除する際は、油汚れに強いアルカリ性洗剤を使用しますが、直接スプレーするのではなく、雑巾やキッチンペーパーに洗剤をつけてから拭き取ります。洗剤が残らないように水拭きし、最後に乾拭きで仕上げます。あらかじめ洗剤をなじませておいた換気扇のパーツは、スポンジや古い歯ブラシでこすり洗いし、乾いた雑巾で水分を拭き取り、再度取り付けて完了です。
コンロやグリルの細かいゴミを、竹串などを使って取り除きます。狭い部分には、中性洗剤をしみ込ませたキッチンペーパーを割り箸に巻きつけたものや、小さなブラシを使うと便利です。洗剤を使ったパーツも、こすり洗いした後に乾拭きで仕上げます。コンロやグリルのパーツは取り外せるので、放置系の洗剤を使って効率よく掃除するのが効果的です。IHコンロは、台所洗剤を含ませた布やスポンジを使って汚れを取り除き、最後に水拭きと乾拭きで仕上げます。
冷蔵庫や電子レンジなどは、食器洗剤を混ぜたぬるま湯に浸し、固く絞ったぞうきんで水拭きします。電子レンジの汚れがなかなか落ちない場合は、ぞうきんを庫内に入れて加熱した後に拭き掃除を行いましょう。最後に、水拭きと乾拭きで仕上げます。
⑨お風呂・浴室の掃除をする
浴室の掃除では、まず⑤でなじませたカビ取り剤を擦り洗いをした後に、他の箇所の掃除を行います。カビ取り剤が他の洗剤と混ざると塩素系ガスが発生する恐れがあるため、カビ取り剤が残らないよう、しっかり洗い流しましょう。
浴室には皮脂汚れ、水あか、湯あか、ピンクヌメリ、黒カビなど、さまざまな種類の汚れが蓄積します。軽い汚れであれば普段使っている中性洗剤で十分に落とせますが、頑固な汚れには、汚れの種類に応じた専用の洗剤を使うのが効果的です。
・皮脂汚れ:中性洗剤・酸性洗剤
・水あか・石けんかす:中性洗剤・酸性洗剤
・床の黒ずみ・湯あか:クレンザー
・黒カビ:塩素系漂白剤
上記を参考に、汚れの種類に応じた洗剤を利用して、お風呂を掃除してみてください。
⑩トイレの掃除をする
トイレの大掃除を始める前に、装飾品やマット、スリッパ、トイレットペーパーなど、トイレ内のすべての物を一度取り出しておきましょう。マットやスリッパ、ペーパーホルダーカバーは、必要に応じて洗濯や買い替えを行ってください。掃除の順番は、天井、便器や便座、タンク、壁、そして床へと進めるとスムーズです。
天井の掃除にはハンディモップを使用し、換気扇周りは掃除機でホコリを落とします。換気扇内部の汚れはトイレクリーナーでしっかり拭き取りましょう。
あらかじめ洗剤をなじませておいた便器は、ブラシで念入りに擦り、汚れをしっかり落とした後に水を流します。タンクや壁も汚れがつきやすい場所なので、中性洗剤と雑巾を使って丁寧に拭き掃除を行います。便器、床、そして見落としがちなドアノブやペーパーホルダーは、トイレクリーナーでしっかりと拭き上げましょう。
⑪洗面所・洗濯機の掃除をする
水回りの最後に、洗面所と洗濯機の掃除をしましょう。まず、洗面所の棚にあるものを全て取り出し、不要な物を処分しましょう。洗面所は壁、鏡、収納棚、蛇口、洗面ボウルの順に掃除を進めます。
壁や収納棚には住居用洗剤を使い、蛇口や洗面ボウルには浴室用洗剤を用いて、汚れを落とします。鏡は、軽い汚れであれば水拭きと乾拭きで十分ですが、汚れがひどい場合はクエン酸などのアルカリ性洗剤を使うと効果的です。
頑固な水あかは、水を含ませたメラミンスポンジで擦り、最後に乾拭きします。黒ずみが気になる部分には、アルカリ性住居用洗剤を塗布した後、メラミンスポンジを使って汚れを落としましょう。最後に、掃除機や住居用洗剤を使って床をきれいにします。
洗濯機の掃除では、取り外せるパーツをぬるま湯に浸け、古い歯ブラシで擦り洗いします。洗濯槽には洗濯槽クリーナーや塩素系漂白剤を投入し、洗浄コースで洗浄します。洗浄コースがない場合は、通常の洗濯コースでも問題ありません。
洗濯機の下部にはホコリや髪の毛が溜まりやすいですが、ハンガーにストッキングを巻いたもので拭くと簡単に取り除けます。最後に、洗濯機全体を水拭きして仕上げます。
⑫リビング・寝室・各部屋の床や棚などを拭き掃除する
②と③でリビングや寝室などは、ある程度の掃除が完了しているため、あとは各部屋の床や棚の拭き掃除を行います。基本的に水拭きで掃除しますが、汚れがひどい場合には中性洗剤を薄めたぬるま湯に浸し、固く絞ったぞうきんで拭き取ります。床は、お掃除シートを装着したフローリングワイパーを使うと効率的です。
スリッパやラグは、汚れや破損などを確認し、必要に応じて洗濯したり買い替えたりすると良いでしょう。
⑬玄関の掃除をする
玄関の掃除を始める際には、まず下駄箱にしまっている靴や、傘立てなど、玄関にある物をすべて取り出します。
下駄箱の中にたまった砂や小石などを掃き出し、その後ぞうきんで水拭きします。下駄箱の中が乾いた後にエタノールをスプレーしておけば、カビや嫌な臭いを防げます。
玄関の床は、細かい砂や小石、泥などの汚れをしっかりと掃き出し、少量の水を撒いてデッキブラシで擦ります。仕上げに乾いたぞうきんで水分を拭き取り、玄関ドアを開けて乾燥させれば完了です。掃除が終わり、しっかり乾いた後に、取り出した物を元の位置に戻しましょう。
ただし玄関の床がコンクリートや大理石などの場合、水や洗剤が使えない可能性があります。事前に材質を確認し、必要に応じて目立たない場所で試してから、掃除を進めるようにしましょう。
⑭ベランダの掃除をする
最後に、ベランダを掃除します。風が強い日や晴天の日は、砂やホコリが舞い上がりやすく、近所に迷惑をかける可能性があるため、できるだけ避けるべきです。ベランダ掃除は、風が穏やかで、湿気の多い曇りの日に行いましょう。
まずは、ほうきや掃除機を使って砂やホコリ、ゴミを取り除きます。ただし濡れたゴミを掃除機で吸い込むと故障の原因になるため、注意が必要です。
次に、薄めた住居用洗剤を床に撒いてデッキブラシでこすり、水で汚れを流します。仕上げに水切りワイパーで水を取り除き、手すりやサッシをぞうきんで拭けば完了です。
マンションや賃貸の場合、ベランダでの水撒きが禁止されている可能性があります。その場合は、ほうきや掃除機でゴミを取り除き、手すりやサッシをぞうきんで拭く程度に留めると良いでしょう。
年末の家の大掃除を成功させるコツ

ここからは、年末の家の大掃除を成功させるコツを紹介します。内容は、以下の通りです。
・時間を決めて大掃除をやる
・洗剤のつけ置き時間も考慮する
・大掃除は「上から下」「奥から手前」の基本の順番を意識する
・簡単に大掃除を済ませたいならプロの力を借りるのもおすすめ
それぞれを詳しく見てみましょう。
時間を決めて大掃除をやる
ひとつ目のコツは、時間を決めて大掃除に取り組むことです。大掃除に集中するあまり、1箇所に時間をかけ過ぎてしまうと、大掃除が終わらないまま新年を迎えてしまう恐れがあります。
先ほども述べた通り、大掃除を効率よく進めるためには、完璧を目指さない・7割〜8割程度できていれば十分と考えることが重要です。1箇所あたりの掃除時間を決め、完璧ではなくても時間がきたら次の箇所を掃除することを意識しましょう。
洗剤のつけ置き時間も考慮する
大掃除には、放置系掃除が必要な場所が多く、放置時間を考慮したうえで、大掃除のスケジュールを組む必要があります。
とくにキッチンの頑固な油汚れ、浴室の落ちにくい黒カビ、トイレの便器の黄ばみや尿石は、放置系掃除が必要です。大掃除を成功させるためにも、午前中の早い時間に洗剤をなじませておき、その放置時間中に他の場所の掃除を進めるとよいでしょう。
大掃除は「上から下」「奥から手前」の基本の順番を意識する
これまで述べたように、大掃除は「上から下へ」「奥から手前へ」の順で進めることが基本です。この手順を守らないと、一度きれいにした場所にまたホコリや汚れがつき、再び掃除する必要がでてきます。
まず天井や棚の上など、高い場所のホコリや汚れを下に落とし、最後に床を掃除することが重要です。また奥の部屋から掃除を始め、掻き出したホコリやゴミを玄関に掃き出すようにしましょう。この基本的な手順を守ることが、大掃除を成功させる重要なポイントです。
簡単に大掃除を済ませたいならプロの力を借りるのもおすすめ
大掃除を手軽に済ませたいなら、プロの力を借りるのをおすすめします。年末に自分で大掃除をするのは、決して簡単なことではありません。また、「仕事や家事・育児で時間が取れない」「忙しい年末に家族の協力が得られず、一人で大掃除をしなければならない」という家庭も多いでしょう。
プロの掃除は、家全体の掃除をお願いするのはもちろん、自分では難しい場所だけを依頼することもできます。大掃除の負担を軽減できれば、年末の忙しさを乗り越えられるでしょう。大掃除で疲弊してしまう前に、ぜひ掃除のプロの利用を検討してみてください。
掃除のプロ「ベアーズ」のハウスクリーニングについて詳しく見る
大掃除ならベアーズのハウスクリーニングにお任せください

年末の手間のかかる大掃除は、創業20年以上で累計250万件以上の実績を持つ家事代行・ハウスクリーニングの「ベアーズ」にお任せください。
ベアーズのハウスクリーニングでは、専門の清掃スタッフが各清掃箇所の汚れや状態に合わせて適切な洗剤や機材を選び、徹底的に掃除します。また、ベアーズのスタッフは清掃技術だけでなく、マナーやお客様対応についても徹底した研修を受けているため、初めての方でも安心して依頼できる点が魅力です。
さらに、サービス終了後30分以内のフォローコールや手直し保証がついており、信頼性の高さもベアーズの強みです。今年の年末の大掃除に困っている方は、ぜひベアーズを検討してみてください。
まとめ

年末の大掃除を効率よく進めるためには、完璧を求めすぎず、無理のない範囲で進めることが重要です。大掃除に何時間も時間をかけてしまうと、気力も体力も尽き果ててしまい、その他の年末の準備がおろそかになってしまう可能性があります。大掃除のコツをしっかり押さえ、時間の節約につなげましょう。
また掃除の順番は「上から下へ」「奥から手前へ」が基本です。ホコリや汚れが再び付着しないよう、基本をしっかり守りましょう。放置系掃除は、午前中の早い時間に取り掛かり、放置時間を使って他の場所の掃除を進めれば、時間を有効活用できます。
大掃除を行う際の注意点は、スケジュールとチェックリストを作り、それをしっかり活用することです。大掃除で使用する洗剤は混ぜると危険なものがあるため、注意書きを必ず確認するようにしましょう。
マンションのベランダや玄関は、水を撒くことを禁止している場合があります。掃除場所に使われている素材には、水や洗剤が使えないものもあります。予期せぬトラブルにならないよう、これらを事前に確認しましょう。
大掃除の負担が大きい場合は、プロの清掃サービスを利用すると良いでしょう。家事代行の「ベアーズ」は、20年以上の実績を持ち、プロのスタッフが適切な洗剤や機材で徹底的に掃除を行います。信頼性の高いサービスを活用し、忙しい年末を乗り越えましょう。
 Related
-関連記事-
Related
-関連記事-
-

ベアーズの料理代行体験プランを使ってみた正直レビュー|在宅育児がぐっとラクに
ベアーズの料理代行体験プランを、在宅で9ヶ月の子どもを見ながら実際に利用。初回限定プランの内容や当日
ベアーズの料理代行体験プランを、在宅で9ヶ月の子どもを見なが
2026.01.20
-

【体験レビュー】冬休み初日にベアーズのベビーシッター体験プランを使ってみた
ベアーズのベビーシッター体験プランを、業務委託パートナーの筆者が実際に利用。冬休み初日に年少(4歳)
ベアーズのベビーシッター体験プランを、業務委託パートナーの筆
2025.12.29
-

【体験レビュー】おそうじ美人GREENで母へ贈る、エアコンクリーニング体験
家事代行のベアーズが提供するハウスクリーニングギフト「おそうじ美人GREEN」。母へのプレゼントとし
家事代行のベアーズが提供するハウスクリーニングギフト「おそう
2025.10.31
-

【体験レビュー】おそうじ美人RED母の日や妻・義母への感謝を伝える体験型ギフトとは?
「おそうじ美人RED」はベアーズの家事代行ギフト。掃除・洗濯・料理など3時間プロに任せられる体験型プ
「おそうじ美人RED」はベアーズの家事代行ギフト。掃除・洗濯
2025.09.03
-

エアコンクリーニングは効果絶大!メリットや業者選びのポイントを解説
「エアコンクリーニングは必要?どんな効果があるの?」 このような疑問にお答えする記事です。 ...
「エアコンクリーニングは必要?どんな効果があるの?」 この...
2025.06.06
-

【産後の家事代行体験記】二児育児スタートの日に頼ったら大正解だった話
産後の心身の負担を少しでも軽くするために、家事代行と育児サポートを活用してみた30代ママの体験記。産
産後の心身の負担を少しでも軽くするために、家事代行と育児サポ
2025.05.03
![]() Pick Up
-ピックアップ-
Pick Up
-ピックアップ-
-

【体験談】ベアーズの家事代行初回お試しプランは、快適な暮らしへの第一歩
ベアーズの「家事代行初回お試しプラン」の体験談をHさんにインタビュー。共働きで1歳の娘を育てるHさん
ベアーズの「家事代行初回お試しプラン」の体験談をHさんにイン
2023.01.19
-

福利厚生の事例8選|従業員の満足度が高いユニークな福利厚生とは
企業が活動するにあたり、従業員は最も重要な財産といえます。優秀な人材が長く働きやすい環境を築くため...
企業が活動するにあたり、従業員は最も重要な財産といえます。...
2022.12.22
-

冷房の使い始めに注意!エアコン掃除や試運転がポイント!【クリーニングサービス体験談も】
夏への準備、エアコンは試運転した方がいいって本当? 季節は5月。夏はまだ先のこと……と思って...
夏への準備、エアコンは試運転した方がいいって本当? ...
2022.05.09
-

【体験談】子どもと過ごせる時間が増えた!家事代行は自分を大切にするためのサービス
こんにちは、家事代行のベアーズです。 共働き夫婦の中には、「仕事と育児で忙しくて家事まで手が...
こんにちは、家事代行のベアーズです。 共働き夫婦の中...
2022.02.10
-

【体験談】家事代行を頼んで時間と心にゆとりができた!帰宅の瞬間が癒しに
こんにちは、家事代行のベアーズです。 オフィスで働くOさん。ご夫婦で共働き...
こんにちは、家事代行のベアーズです。 ...
2022.01.31
-

ウェルビーイングに貢献する福利厚生とは?社員の生産性を高める5つの例
近年、働く上でのウェルビーイング(幸福感や満足感)の重要性が注目されるようになってきました。従業...
近年、働く上でのウェルビーイング(幸福感や満足感)の重要...
2022.01.07