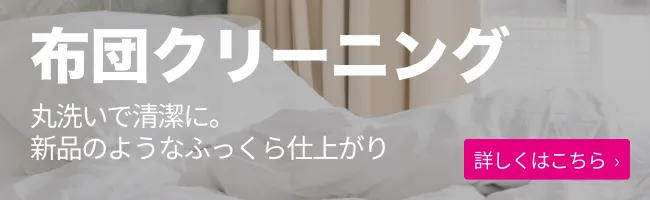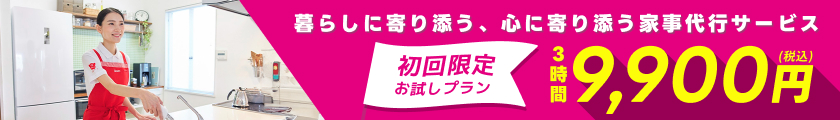布団やシーツ洗濯の頻度は?洗うタイミング・洗い方・干し方・注意点を解説
お役立ち全般
更新日:2025.06.22

布団をいつ洗濯したらいい?布団を洗う頻度がわからない…と悩んでいる方も多いでしょう。布団は肌に直接触れるものであり、汗や皮脂、ホコリが蓄積しやすアイテムです。清潔な状態を保つためにも、定期的なお手入れが欠かせません。
そこで今回は、布団を洗濯する理想的な頻度をわかりやすく解説します。布団の正しい洗い方・干し方・注意すべきポイントも紹介していますので、ぜひ参考にしてください。
寝具の汚れにお悩みですか?累計250万件を超える豊富な実績のあるベアーズがあなたの寝具をピカピカにします。
▶︎【ベアーズの洗濯・クリーニングサービスについて詳しく見る】
目次
布団を洗濯すべき理由とは?雑菌・ダニ・においのリスク

私たちが毎日使う布団には、見えない汚れや菌がたくさん付着していると言われています。それは、どのようなものなのでしょうか?
人は寝ている間にコップ1杯分の汗をかくとされていますが、その汗はニオイや雑菌を繁殖させる原因となります。また、汗に含まれた皮脂などはダニの餌になるとも言われています。ダニは皮膚の角質やフケをエサにして増え、死骸やフンがアレルギーや喘息の原因につながるのです。
さらに、雑菌特有のにおいは不快感を招くだけでなく、睡眠の質を低下させ、肌トラブルや呼吸器への負担を引き起こす可能性が考えられます。こうした健康リスクを抑えるためにも、定期的な布団の洗濯が必要です。
寝具(布団やシーツ)を洗濯する理想の頻度・目安

以下では、寝具類を洗濯する理想の頻度・目安について解説します。
・掛け布団・敷布団の洗濯頻度は年2回
・シーツの洗濯頻度は週1回
・枕の洗濯頻度は2~4週間に1回
・毛布の洗濯頻度は月1回
・羽毛布団の洗濯頻度は5〜7年に1回
それぞれを詳しく見てみましょう。
掛け布団・敷布団の洗濯頻度は年2回
掛け布団や敷布団の理想的な洗濯の周期は、年に2回、春と秋の気候が穏やかで乾きやすい時期が適しています。
春は冬の間にたまった汚れをリセットするタイミング、秋は夏場の汗や湿気を落とす絶好の機会です。洗濯後はしっかりと天日干しし、中までしっかり乾かすようにしましょう。
乾燥が不十分だと、菌やカビが繁殖するリスクが高いため注意が必要です。また、布団の素材によっては自宅で洗えないため、洗濯表示の確認を徹底しましょう。
シーツの洗濯頻度は週1回
肌トラブルやアレルギーの原因となるダニや雑菌の繁殖を防ぐためにも、シーツは週に1回の洗濯が理想と言われています。
シーツは寝ている間にかいた汗や皮脂が直接染みこむため、寝具の中でも特に汚れやすいアイテムです。特に夏場や寝汗をかきやすい人、小さな子どもがいる家庭では、こまめに洗濯したほうが良いでしょう。
忙しいときは、洗い替え用のシーツを複数用意しておくと便利です。肌に直接触れるシーツは快眠の質にも大きく関わるため、最低でも週1回は洗濯するようにしましょう。
枕の洗濯頻度は2~4週間に1回
枕は、衛生面を保つためにも2〜4週間に1回の頻度で枕本体、週1回の頻度で枕カバーを洗濯するのが望ましいです。
枕は顔や頭皮が長時間直接触れるため、皮脂や髪の汚れ、化粧品の成分などが蓄積しやすく、そのまま放置すると、においや黄ばみ、ダニやカビの繁殖につながる可能性があります。
洗濯可能な枕は、中性洗剤を使って優しく洗い、しっかりと中まで乾かすようにしましょう。また、乾かす際は風通しのよい場所で天日干しにすると、においも軽減されて清潔感が保てます。
枕の衛生状態は睡眠の質にも大きく影響するため、定期的なお手入れを習慣化することが大切です。
毛布の洗濯頻度は月1回
毛布は、月に1回を目安に洗濯するのが理想です。毛布は体に密着するため、寝ている間の汗や皮脂、空気中のホコリを吸収しやすく、放っておくとにおいやアレルゲンの原因になります。
最近では、家庭用洗濯機で丸洗いできる毛布も増えており、比較的簡単にお手入れできます。洗濯時は洗濯ネットを使い、弱水流や「毛布モード」で洗濯すると型崩れしにくくおすすめです。乾かすときは天日干しでしっかり乾燥させるか、乾燥機を併用する良いでしょう。
羽毛布団の洗濯頻度は5〜7年に1回
羽毛布団は保温性に優れた高級寝具ですがデリケートなため、自宅での洗濯は避け、5〜7年に1回を目安に専門のクリーニング業者に依頼するのがおすすめです。
長年使っていると汗や皮脂、ホコリなどが内部に蓄積されていきます。衛生面だけでなく、羽毛の膨らみや弾力を維持する意味でも、洗濯はプロにお任せしましょう。
なお、使用頻度が高い冬の終わりに出すと、次のシーズンも気持ちよく使えます。羽毛布団の寿命を延ばすためにも、適切な頻度で丁寧なケアを心がけましょう。
寝具の洗濯をプロに依頼するならベアーズにお任せください。累計250万件を超える豊富な実績のあるベアーズがあなたの寝具をピカピカにします。
布団を洗濯する時期は春~初夏・秋頃がおすすめ

布団を洗濯するタイミングは、春〜初夏、秋など「乾燥しやすく気温が安定している季節」が適しています。
春は冬の間に溜まった汗や皮脂、ダニの死骸などをリセットする絶好のタイミングです。一方、秋は夏の寝汗や湿気によるカビ・臭い対策に効果があります。
どちらの時期も天候が安定しており、2〜3日連続で晴れる日が多いため、布団の中までしっかり乾かせるでしょう。特に、湿気が大敵の掛け布団や敷布団は梅雨や真冬は乾きにくく、雑菌やカビの原因になりやすいため注意が必要です。
天気予報を事前に確認し、日差しと風通しのよい日を選んで洗濯・干す作業を行いましょう。
布団を洗濯する方法

布団の取り扱い絵表示に洗濯機マークや手洗いマークが付いていれば、家庭で洗うことができます。それでは実際に、「洗濯機を使った布団の洗い方」と「浴槽を使った布団の洗い方」を紹介します。
それぞれを詳しく見てみましょう。
洗濯機を使った布団の洗い方
洗濯機を使って布団を洗う前に、次のような準備が必要です。
最初に「洗濯機の容量がこれから洗う布団の大きさに合っているのか」を取扱説明書などで確認します。布団の大きさが洗濯機の洗える容量よりもオーバーすると、故障の原因になることがあります。もし、自宅の洗濯機の容量が小さいようであれば、大きいものが洗えるコインランドリーを利用してみるのも1つの方法です。
次に準備するものは「寝具用の洗濯ネット」です。布団の型崩れや傷みを防ぐためにも、洗濯ネットに入れて洗濯するようにしましょう。使い方は、布団を縦方向に3つ折りにし、空気を抜きながらクルクルと丸めて洗濯ネットに入れます。
最後の準備です。布団にムラなく洗剤を行き渡らせるためにも、洗濯槽に水を少し張り、洗剤を入れてよく溶かしておきましょう。
いよいよ洗濯開始です。洗濯ネットに入った布団を洗濯槽の中にバランスよく入れ、布団(毛布)洗いコースがあればそれを選択してスタートボタンを押します。
布団(毛布)洗いコースが無ければ、大物洗いや手洗いコースなどを選ぶといいでしょう。手動の場合は、洗濯時間6分、すすぎ2回、脱水6分程度がおすすめです。
浴槽を使った布団の洗い方
浴槽を使って布団を洗う場合、まずは布団に水かぬるま湯のシャワーをかけて予洗いします。この予洗いで、表面のホコリやペットの毛などを落としておきましょう。予洗いが済んだら、布団を縦方向に3つ折りにし、クルクルと丸めて布団内の空気を軽く抜いておきます。
次に、浴槽の半分くらいまでぬるま湯を張ります。そこに洗剤を入れて、よく溶かしてから布団を浴槽内に入れ、十分に水を吸わせます。そして、手や足を使って上からまんべんなく優しく押し洗いしましょう。
全体的に押し洗いが済んだら、水を入れ替えて再び押し洗いをします。これを2~3回繰り返せば、すすぎが完了です。
布団を洗濯したあとの正しい干し方

浴槽で洗った場合、水を吸った布団はかなり重くなっていますので、浴槽の縁に30分~1時間くらい掛けておきましょう。ある程度脱水ができたら、いよいよ布団干しです。
水分を吸った布団はかなり重量があります。物干し竿に布団を掛けて干す場合は、2本の竿にまたがるようにM字型にして掛けると重みが分散されます。布団洗濯バサミを使って、布団が風で落ちないように留めておきましょう。
布団は、直射日光による色落ちやダメージなどを防ぐためにも影干しがおすすめです。陰干しが難しい場合は、布団の上に大きな布を掛けて乾かしましょう。
布団を洗って干す場合は、しっかりと乾燥させないとカビやダニの発生原因になることもあります。洗濯当日から2、3日後まで天気が続くような日を選んで洗い、干すといいでしょう。
布団の洗濯とあわせて実践したい!ダニ・カビ対策の基本

以下では、布団の洗濯と合わせて実践したいダニ・カビ対策について解説します。
・天日干しにする
・除湿シートを活用
・こまめに掃除機をかける
・布団乾燥機を使う
・長期保存前に洗う
それぞれを詳しく見てみましょう。
天日干しにする
ダニの繁殖を抑えるためには、天日干しがおすすめです。日光に含まれる紫外線には、ダニの繁殖を抑える効果が期待できます。さらに、布団にこもった湿気やにおいの軽減にもつながります。
【手順】
1.晴天で湿度の低い日を選ぶ
2.物干し竿に布団をM字型にかけて干す
3.両面を均等に干すため、2〜3時間ごとに裏返す
4.4〜5時間程度しっかり干す
5.干し終わったら布団たたきで軽く叩いてホコリを除去する
干す時間帯は午前10時から午後3時が最適です。
除湿シートを活用
カビの発生を避けるためにも、敷布団やマットレスの下に除湿シートを敷くのがおすすめです。除湿シートは、床からの湿気を吸収しカビの発生を防げるアイテムで、湿度が高まりやすい梅雨時期や冬場に役立ちます。
繰り返し使えるタイプや湿気が溜まると色が変わるタイプなどもあり、手軽に取り入れられます。
【手順】
1.布団の下、敷き布団と床の間に除湿シートを敷く
2.使用後は陰干しして湿気を飛ばす
3.使用頻度や湿度に応じて定期的に交換または干し直す
こまめに掃除機をかける
布団表面にはホコリやダニの死骸、フケなどが溜まりやすく、これらがアレルゲンの原因になります。週に1~2回を目安に、布団専用ノズルや粘着シートを使って掃除機をかけると、見えない汚れもしっかり除去できます。特に肌が触れる部分は丁寧に行いましょう。
【ポイント】
・週1回を目安に布団に掃除機をかける
・掃除機はヘッドに布団用ノズルを装着する
・表面全体をゆっくり、一定方向にかける
・可能であれば裏面にもかける
布団乾燥機を使う
天気に左右されずに布団を乾燥させたい場合は、布団乾燥機の利用がおすすめです。高温の温風でダニを死滅させる効果があり、消臭・湿気対策にも有効です。定期的に使用すれば、ふんわりとした寝心地と清潔感を維持できます。
【手順】
1.布団乾燥機のマットを布団の中に差し込む
2.乾燥モードまたはダニモードを選択する
3. 所定の時間(1〜2時間)運転する
4.使用後は風を通して湿気を逃がす
長期保存前に洗う
季節の変わり目で布団をしまう前には、洗濯・乾燥を徹底することが大切です。汚れや湿気を残したまま収納すると、カビや悪臭の原因になります。保存前には防虫剤や除湿剤を一緒に入れると、より安心です。
洗濯できる布団の種類とは?

布団の素材によっては、クリーニングが難しいものもあります。以下では、素材別の特徴や、洗濯の注意点を紹介します。
・羊毛が使われた布団
・羽毛が使われた布団
・ポリエステルが使われた布団
それぞれを詳しく見てみましょう。
羊毛が使われた布団
羊毛に防虫加工を施し、製綿したものです。掛け布団にも敷き布団にも適した素材で、吸放湿性が特に優れていると言われています。自宅での洗濯は、基本的にはしないほうが良いとされています。自宅での洗濯では、繊維同士が絡み合い大きく縮んでしまう可能性が高いようです。
部分的な汚れであれば、あまり水に濡れすぎないよう注意し、やさしく手洗いすることが可能と言えますが、全体的な汚れやニオイが気になる場合は、布団のクリーニングに出すことをおすすめします。
羽毛が使われた布団
羽毛に防虫加工を施し、製綿したものです。ガチョウ・アヒルなどの水鳥の羽毛が原料とされています。保温性が抜群によく、お手入れも比較的簡単なので、今では掛け布団のスタンダードになっています。
最近では、自宅で洗える羽毛布団も多く販売されおり、自宅での布団丸洗いに挑戦する方も多いでしょう。その際、最初に必ずチェックして欲しいのは洗濯表示です。水洗いマーク、手洗いマーク、洗濯機マークが記載されていたら、その布団は洗っても大丈夫と言えます。
しかし水洗いマークにバツが付いているものは、そもそも水洗いができない布団です。この場合は、布団のクリーニング店や布団の販売店など、専門知識のある方に一度相談したほうが良いでしょう。
ポリエステルが使われた布団
水と石油と石炭を原料とした繊維で、近頃はポリエステルが主流と言えます。洗う事を前提に作られた化学繊維のものもあり、洗濯に強いタイプも多く販売されています。こまめに洗濯が可能なので、アレルギーの方や清潔志向の方にはおすすめと言えます。
布団を洗濯する際の注意点・チェックポイント

以下では、布団を洗濯する際の注意点・チェックポイントについて解説します。
・自宅での洗濯を推奨していない素材もある
・洗濯後は中までしっかり乾燥させる
・種類・素材によって洗濯方法が異なる
・天気予報をチェックし晴天が続く日を選ぶ
・干す際は風通しがよく乾きやすいM字型にする
それぞれを詳しく見てみましょう。
自宅での洗濯を推奨していない素材もある
布団には、家庭用洗濯機が使用できない素材のものもあるため注意が必要です。洗濯表示に「家庭洗濯不可」の素材は、無理に洗うと縮みや型崩れ、劣化を招きます。
特に、羊毛(ウール)、シルク(真綿)、ウレタンフォーム入り、抗菌・防ダニ加工済みなどは注意が必要です。これらは水に弱く、生地の風合いや中綿の構造が崩れやすいため、自宅で洗濯せず専門業者へのクリーニング依頼をおすすめします。
洗濯後は中までしっかり乾燥させる
布団を洗濯した際は、必ず中までしっかり乾燥させましょう。布団は見た目が乾いていても中綿に湿気が残りやすく、放置するとカビやダニの繁殖を招きます。
洗濯後は晴天を選び、物干し竿にM字型に掛けて風通しを良くし、日光と風で4~6時間ほどかけてしっかり乾燥させましょう。天候が悪い場合や真冬は布団乾燥機を併用し、高温の温風で内部まで乾かすのが効果的です。
乾き具合は中まで手で押して確認し、完全に乾燥しているかをチェックしましょう。
種類・素材によって洗濯方法が異なる
布団の素材をチェックし、洗濯機や手洗いなどの洗い方を確認しましょう。布団の素材ごとに洗い方を変えないと、機能を損なったり素材を傷めたりするリスクがあります。
特に、ポリエステル製や化繊マイクロファイバー布団は洗濯機で丸洗い可能ですが、厚みや容量に注意し「布団コース」や「大物洗いモード」を選びましょう。綿布団は、手洗いかコインランドリーの大型機が安心です。
羽毛布団は、プロに依頼するのが基本です。必ず洗濯表示で「手洗い可」「ネット使用」など指示を守り、中綿が偏らないようやさしく洗いましょう。
天気予報をチェックし晴天が続く日を選ぶ
洗濯前に天気予報を確認し、2~3日以上晴れマークが並ぶタイミングを選んで計画しましょう。2~3日連続で晴れ予報が出ていれば、1日で完全に乾かなくても翌朝も同じ時間帯に干せるので安心です。
梅雨時期や真冬は湿度が高く乾きにくいため、布団乾燥機や除湿機を活用すると良いでしょう。
干す際は風通しがよく乾きやすいM字型にする
布団をM字型(折り目が山になる形)に掛けると、中央に空間ができて風が通りやすくなり、布団の厚み全体を均一に乾燥できます。具体的には、物干し竿に布団の真ん中を山折りにかけ、左右が均等に垂れるよう調整しましょう。
布団乾燥機を併用する場合も、同様にM字型でセットすると内部まで熱風が届きやすくなります。途中で裏返して表裏両面を均等に乾かすと、水分ムラを防げます。干し時間は4〜6時間を目安にしましょう。
布団の洗濯が難しいときは布団クリーニングがおすすめ

布団の汚れが気になるときに一番おすすめなのは、専用のクリーニングです。専用の大型の洗濯機で、中綿の汚れをしっかりと落とすことができると言われています。
また、素材を傷つけにくい機材や洗剤、乾燥方法を取り入れており、自宅では大変な布団の洗濯も、クリーニングを利用すれば中まですっきり清潔になるでしょう。
以下では、布団クリーニングの特徴について解説します。
・布団クリーニングの便利なサービス
・クリーニングに出せる布団の種類
・布団クリーニングの料金相場
・布団クリーニングを依頼するペース
それぞれを詳しく見てみましょう。
布団クリーニングの便利なサービス
布団クリーニングサービスでは、クリーニングの申し込みをすると発送キット(梱包用ビニール袋や発送伝票)が届きます。カバーやシーツは全て外し・依頼伝票を記入・名札に名前と電話番号を書いて、布団に取り付けます。
布団を専用の布団袋に入れ、外側のポケットに送り状を入れたら発送準備完了です。あとは発送するだけで、クリーニング完了後にはスッキリ綺麗になった布団が自宅に届きます。
こちらは依頼するクリーニングサービスによっても変わってきますので、よく注意して事前に確認しておきましょう。
クリーニングに出せる布団の種類
布団クリーニングサービスでは、洗える布団は羽毛、羊毛、綿、ポリエステル、ウレタンのものとされています。また、洗えない布団は、シルク、ムートン、ノンキルトの羽毛布団、ポリエステルと記載されています。
こちらは依頼するクリーニングサービスによっても変わってきますので、よく注意して事前に確認しておきましょう。
布団クリーニングの料金相場
布団をクリーニングに出した場合の平均的な料金相場を紹介します。
クリーニング店に羽毛布団を持ち込んだ場合、シングル1枚で5,000~6,000円くらいが相場です。宅配サービスのクリーニング店の場合は送料が料金に含まれていることがあり、シングル1枚9,000~11,000円と、少し高めの料金設定になっていることが多いようです。
ですが1~2枚では割高であっても、3枚以上であれば宅配サービスのほうが安くなることもあります。
どちらのクリーニングの場合でも、キャンペーンやまとめ割引などが適用されることがあります。また、仕上がり日数なども違いがありますので、利用する際にはどちらがいいかを十分にチェックしておきましょう。
布団クリーニングを依頼するペース
布団クリーニングを依頼する頻度の目安は以下のとおりです。
布団の衛生面を考えると半年に1回~1年に1回が理想的ですが、クリーニングの回数が多ければそれだけ布団のダメージも大きくなります。布団をできるだけ長く使いたいのであれば、2、3年に1回程度の期間でクリーニングするのをおすすめします。
布団をクリーニングに出すタイミングは、夏布団から冬布団へ、もしくは冬布団から夏布団へと入れ替える季節の変わり目がおすすめです。次のシーズンに気持ちよく使うためにも、ぜひこのタイミングを逃さないようにしてください。
布団クリーニングなら「ベアーズ」にお任せください

家事代行サービスのベアーズでは、布団がまるで新品みたいにふかふかで清潔になると好評の「ふとん丸洗いクリーニング」サービスを提供しています。
ベアーズのふとん丸洗いのこだわりポイントは以下の通り。
・手洗いではなく、洗いの工程をプログラム化した専用の機械で布団を丸洗いする
・漂白剤や溶剤は使わずに布団生地を傷めることなく洗う
・平面乾燥機を使用し、布団にダメージを与えずに乾かす
また、中性洗剤を使って洗い上げるため、ダウンの羽枝1本1本が絡み合うことなくキレイに仕上げることができます。
ベアーズのふとん丸洗いクリーニングの料金表はこちらです。
【布団クリーニング】
| 布団1枚コース | 13,200円(税込) |
| 布団2枚コース | 15,400円(税込) |
| 布団3枚コース | 17,600円(税込) |
【ロイヤル羽毛コース】
| 羽毛ロイヤルコース1枚 | 36,300円(税込) |
| アイダー羽毛コース1枚 | 55,000円(税込) |
布団の洗濯の頻度に関するよくある質問

以下では、布団の洗濯の頻度に関するよくある質問と回答を紹介します。
・シーツを1ヶ月洗ってなかったらどうなりますか?
・一人暮らしの場合、布団を洗う頻度は?
・冬布団・羽毛布団は毎年洗うべきですか?
それぞれを詳しく見てみましょう。
シーツを1ヶ月洗ってなかったらどうなりますか?
結論から言うと、シーツを1ヶ月洗わないと雑菌やダニが急速に繁殖し、肌トラブルやアレルギー症状を引き起こすリスクが高まります。寝ている間にかく汗や皮脂、フケなどは、雑菌・ダニの餌です。
1週間洗わないだけでもシーツ表面の菌の数は数倍に増えると言われており、1ヶ月放置するとカビ臭や黄ばみが目立ちます。中には、肌に赤みやかゆみが出る場合もあります。
特に、皮脂やフケはアレルギー性鼻炎や喘息の原因につながるため、週1回の洗濯を徹底し、快適な睡眠環境を守りましょう。
一人暮らしの場合、布団を洗う頻度は?
一人暮らしでも布団の洗濯頻度は「アイテム別の目安」を守るのがベストです。一人でも汗や皮脂、ホコリが布団に付着し、放置するとダニや雑菌が増えます。
そのため、掛け布団・敷布団は年2回、シーツは週1回、枕は2~4週間に1回、毛布は月1回を目安にお手入れしましょう。シーツや枕カバーは週1回の洗濯で、清潔を保てます。
冬布団・羽毛布団は毎年洗うべきですか?
冬布団や羽毛布団は、5~7年に1回のクリーニングをおすすめします。羽毛布団はデリケートな素材で、水洗いを繰り返すと中綿が偏ったり、保温性が低下したりする可能性があります。
冬のシーズン終わりには軽く天日干しし、羽毛専用の除菌スプレーを使う程度に留めるのがおすすめです。ただし、使用頻度が非常に高かったり、黄ばみ・においが気になったりする場合は、1~2年に1回のクリーニングを検討しましょう。
まとめ

布団を清潔に保つには、頻度とお手入れ方法の両方を意識することが大切です。まず、シーツは週1回、枕は2~4週間に1回、毛布は月1回、掛け布団・敷布団は年2回、羽毛布団は5~7年に1回を目安に洗濯しましょう。
洗濯前には洗濯表示を必ずチェックし、自宅洗濯が難しい素材はプロのクリーニングを利用します。洗濯後はM字型干しで風通しを良くし、天日干しや布団乾燥機を併用して中綿までしっかり乾燥させることが不可欠です。
布団を長く清潔な状態に保つためにも、ぜひ本記事で紹介した内容を参考に定期的なお手入れを意識しましょう。洗いを検討してみてはいかがでしょうか。
 Related
-関連記事-
Related
-関連記事-
-

母の日のプレゼントに「家事代行」という新しい選択肢を|2026年は感謝の気持ちをカタチに
2026年の母の日は5月11日。お母さん、そして義母や妻に贈るプレゼントに悩んだら、掃除や家事代行な
2026年の母の日は5月11日。お母さん、そして義母や妻に贈
2025.07.29
-

衣替えを楽にする7つのコツ!整理整頓は誰でもかんたんにできる
「衣替えがうまくできない……上手に整理するコツとかあるのかな?」 毎シーズン、気づけば洋服が増えて...
「衣替えがうまくできない……上手に整理するコツとかあるのかな...
2025.02.10
-

家政婦の仕事とは?料金体系や依頼する時の注意点について詳しく解説
共働きの普及とともに需要が増しているのが「家政婦」です。しかし、家政婦の仕事内容や料金体系につい...
共働きの普及とともに需要が増しているのが「家政婦」です。...
2024.07.11
-

「お墓掃除・お墓参り代行」でお盆・お彼岸・年末年始もキレイに保とう
お盆やお彼岸、年末年始など親族でお墓参りをする前に、お墓を綺麗に掃除しておきたいと思う人も多いのでは...
お盆やお彼岸、年末年始など親族でお墓参りをする前に、お墓を綺...
2023.12.22
-

ペットシッターとは?不在中に大事なペットのお世話を任せて長期休みを満喫!
飼い主さんが旅行や出張、入院などでペットを残して家を空けなければいけないケースが時々ありますよね...
飼い主さんが旅行や出張、入院などでペットを残して家を空け...
2023.12.05
-

布団クリーニングと布団リフォーム(打ち直し)の違いとは?新品よりもお得!
布団を長年使用するうちに、変色や湿っぽさが気になることはありませんか?そんなとき、同じグレードの布団...
布団を長年使用するうちに、変色や湿っぽさが気になることはあり...
2023.10.31
![]() Pick Up
-ピックアップ-
Pick Up
-ピックアップ-
-

【体験談】ベアーズの家事代行初回お試しプランは、快適な暮らしへの第一歩
ベアーズの「家事代行初回お試しプラン」の体験談をHさんにインタビュー。共働きで1歳の娘を育てるHさん
ベアーズの「家事代行初回お試しプラン」の体験談をHさんにイン
2023.01.19
-

福利厚生の事例8選|従業員の満足度が高いユニークな福利厚生とは
企業が活動するにあたり、従業員は最も重要な財産といえます。優秀な人材が長く働きやすい環境を築くため...
企業が活動するにあたり、従業員は最も重要な財産といえます。...
2022.12.22
-

冷房の使い始めに注意!エアコン掃除や試運転がポイント!【クリーニングサービス体験談も】
夏への準備、エアコンは試運転した方がいいって本当? 季節は5月。夏はまだ先のこと……と思って...
夏への準備、エアコンは試運転した方がいいって本当? ...
2022.05.09
-

【体験談】子どもと過ごせる時間が増えた!家事代行は自分を大切にするためのサービス
こんにちは、家事代行のベアーズです。 共働き夫婦の中には、「仕事と育児で忙しくて家事まで手が...
こんにちは、家事代行のベアーズです。 共働き夫婦の中...
2022.02.10
-

【体験談】家事代行を頼んで時間と心にゆとりができた!帰宅の瞬間が癒しに
こんにちは、家事代行のベアーズです。 オフィスで働くOさん。ご夫婦で共働き...
こんにちは、家事代行のベアーズです。 ...
2022.01.31
-

ウェルビーイングに貢献する福利厚生とは?社員の生産性を高める5つの例
近年、働く上でのウェルビーイング(幸福感や満足感)の重要性が注目されるようになってきました。従業...
近年、働く上でのウェルビーイング(幸福感や満足感)の重要...
2022.01.07