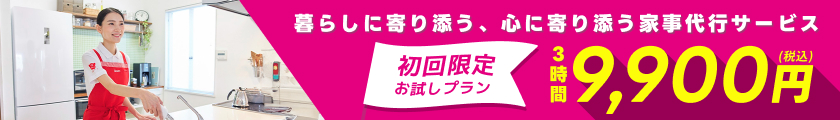仕事・家事を両立するコツ7選|共働き・育児中でも無理せず回せる工夫を紹介
共働き
更新日:2025.06.30

共働きや子育て中の家庭では、「仕事も家事も中途半端になってしまう」「毎日がいっぱいいっぱい」と感じている人も多いのではないでしょうか。女性に偏りがちな家事の負担は、知らず知らずのうちに心身を追い詰めている可能性もあります。
この記事では、そんな忙しい毎日を少しでも楽にするための「仕事と家事を両立する7つのコツ」を紹介します。時短家電や家事代行、分担の見直しなど、今日から取り入れられる実践的な工夫ばかりです。無理なく続けられる両立のヒントを、ぜひ参考にしてください。
仕事と家事の両立にお困りなら家事代行がおすすめです。累計250万件を超える豊富な実績のあるベアーズがあなたの家事を代行します。
目次
家事と仕事の両立が女性に偏る理由

仕事と家事の両立が女性に偏っている背景には、共働き世帯が増加しているにも関わらず、社会的・家庭的に「男性は仕事、女性は家事・育児を担う」という性別役割観が根強く残っている点があげられます。
令和6年版『男女共同参画白書』によると、共働き世帯は増加傾向にあり、昭和60年(1985年)には718万世帯だったのが、令和5年(2023年)時点で1,206万世帯にまで増加しました。一方、専業主婦世帯は減少を続けており、昭和60年(1985年)は936万世帯から令和5年には404万世帯と、共働き世帯のおよそ3分の1にとどまっています。
かつて主流だった「夫が働き、妻は専業主婦」という家庭像は大きく変化し、現在では夫婦共に働くのが当たり前の時代となりました。しかし、夕食の準備や洗濯、子どもの送り迎えなどは妻が担当するケースが多く、家事が「手伝い」ではなく「女性の仕事」として位置づけられがちです。また、子どもの予定管理や買い物リスト作成など「見えない負担」まで妻が引き受けるため、心身へのストレスが蓄積しやすくなっています。
このように、共働きが当たり前になった現代においても、「女性が家事を担うべき」という性別役割の固定観念や、家庭内での分担の偏りが、家事と仕事の両立を女性に偏らせている大きな要因となっています。
参照:男女共同参画白書 令和6年版 共働き世帯数と専業主婦世帯数の推移
仕事と家事の両立が難しい・できない原因

以下では、仕事と家事の両立が難しい原因について詳しく解説します。
・時間が足りない
・分担がうまくいっていない
・予定外のトラブルで計画通りにいかない
・家事の負担が大きい
・仕事・家事に加えて育児の負担もある
それぞれを詳しく見てみましょう。
時間が足りない
女性が疲れてしまう理由として最初に考えられることは「家事に費やすことができる時間が圧倒的に足りないのではないか」ということです。
フルタイムで共働きをしている夫婦の場合、平日は出勤前と帰宅後の時間を家事に費やすことになります。ですが、残業などがあるときは帰宅時間が遅くなり、満足に帰宅後の家事の時間を確保することが難しくなってしまうこともあるでしょう。
また、夫婦共に出張などが頻繁にある場合は、そもそも家事を行う時間を確保することが困難になり、そのできなかった家事が次から次へと溜まってどうすることもできなくなってしまいます。
特に子育て中の30~40代というのは働き盛りであり、仕事でもリーダーを任される機会が増え、仕事の量が急に増えていく年代です。そのため、この年代の共働き夫婦の場合は、共に仕事が忙しくなり、「いつも家事をする時間が足りない」と困窮する事態が起こることが容易に想像できます。
家事分担がうまくいっていない
次に疲れてしまう理由として挙げられるのは「夫婦の家事分担がうまくいっていない場合が多い」ということです。男性が「家事・育児に参画する意識が薄い」という家庭では、女性がたとえ仕事が忙しいという状態であっても、女性側に圧倒的に家事の負担が課せられていることが多いと予想されます。
そのため、女性ばかりが休む暇がなく、仕事と家事に明け暮れるような日々が続くことで、次第に不満が溜まってくるようになります。さらに事態が悪化すれば、やがて女性が心身共に疲弊し、ついには会社を辞めて主婦業に専念するという道を選ぶことになり、家事と仕事の両立を諦めてしまうという最悪のケースも考えられます。
予定外のトラブルで計画通りにいかない
両立が難しい原因は、日々の中で起こる「予定外のトラブル」にもあります。子どもの発熱や保育園からの呼び出し、残業や電車の遅延など、突発的な問題を事前に防ぐ方法はありません。
時間通りに進めようとしても、トラブルへの対処で一気にペースが乱れてしまいます。
そんな日は、どれだけ計画を立てても思い通りに進まないものです。
「完璧にやる」よりも、「スケジュールが崩れたときにどうやって取り戻すか」を考えておく必要があります。
家事の負担が大きい
最後に疲れてしまう理由として挙げられるのは、「家事の守備範囲が広くて負担が大きい」という点です。そもそも家事というものは、家の中で発生するすべての仕事を含むため、掃除や料理、洗濯といったメインの作業だけでは終わりません。
日用品の補充やゴミ出し、郵便物の整理など、仕事は際限なくあると思ってもいいでしょう。そのため、家事の負担は想像以上に大きく、女性が仕事と家事の両立をしたいと思っても、なかなか思うようにはいかない原因になっています。
共働き夫婦の家庭で家事の負担が大きいと感じているのであれば、すこし肩の力を抜いて、時短術などを使ってうまく”手抜き”をしてみてはいかがでしょう。最近は「ゆる家事」という言葉も広まっています。
また、日常的な家事は平日に行い、休日にまとめて残った家事を行うなどの工夫も必要でしょう。しかし、家事をどこまでさぼるか、またどこまで妥協するかの線引きは、なかなか難しいことでもあります。
仕事・家事に加えて育児の負担もある
子育て世帯では、仕事と家事に加え、育児の負担も発生します。特に妻は多くのタスクを抱え、時間や体力だけでなく感情まで消耗し、精神的な余裕を失いがちです。
子どもが小さいうちは、夜泣きによる睡眠不足のまま出勤し、帰宅後は夕食の準備・お風呂・寝かしつけと続くため、自分の時間や心の余裕がほとんどなくなります。
このような状況では「もっとがんばろう」と自分を追い込むより、どこでサポートを得られるか、どの負担を減らせるかを考えることが重要です。育児は一人で背負い込まず、家族や周囲に頼る力を身につけましょう。
仕事・家事を両立させるコツ7選

ここからは、仕事・家事を両立させるコツを7つ紹介します。
・時短家電を活用する
・お互いが得意なことを担当する
・ネットスーパーや宅配を利用する
・家事の優先順位を決める
・両立しやすい仕事への転職を検討する
・制度を活用する
・家事代行サービスに頼る
それぞれを詳しく見てみましょう。
時短家電を活用する
まずは「時短になるような家電を活用する」という方法を考えてみましょう。さまざまなメーカーが家事をサポートするような家電を多数市販していますので、それらを進んで活用することで、かなりの家事が効率化すると考えられます。
具体的な電化製品を例に挙げてみると、「自動調理器」や「お掃除ロボット」などを使うことで、自分の手を動かさなくても料理や掃除ができるようになります。また、「食洗器」は面倒な食器洗いから乾燥までをすべて自動で行い、手洗いよりも水道水の節約になります。
吸引力の強い「コードレスクリーナー」は、従来の掃除機よりも軽量に設計されている物が多く、腕や肩に余計な負担が掛からず電気コードも邪魔にならないため、効率的で楽に掃除をすることができるようになります。
このように、多種多様な家電製品を上手に選んで活用することで、家事にかける時間をかなり短くすることができると予想されます。
お互いが得意なことを担当する
次に夫婦で考えていくべきことは、共働きの家庭では家事の分担を「お互いが得意であることを担当する」ように工夫することです。たとえば、料理が苦手でも整理整頓が得意な夫には、料理ではなく洗濯物を畳んでしまうといった作業を担当してもらうと作業がはかどります。
また、早寝早起きが得意などちらかのほうが、朝食作りやゴミ出しなどの早朝の家事を担当するという方法もいいでしょう。このように夫婦が互いに得意なことを担当するように双方で話し合い、バランスよく分配することで、女性ばかりが疲れやストレスを感じることなく家事を進めることができるようになります。
ネットスーパーや宅配を利用する
毎日の買い出しや食事の用意などは、思った以上に時間のかかる家事です。そこで、「ネットスーパーや宅配を利用する」ことも検討してみてはいかがでしょう。ネットスーパーはインターネットを使って手軽に食材を注文するだけで、自宅まで食材を届けてくれるシステムです。
また、時短料理が可能な「料理キット」などを届けてくれる宅配サービスなどもありますので、それを利用してみてもいいでしょう。このような料理キットなどは、使う分だけ人数分の野菜や肉などがセットされていますので、無駄な食材が出ることがなく経済的です。
このようにしてネットスーパーや宅配サービスを効率よく利用することで、買出しの時間が省略され、無駄な買い物が無くなり、重い荷物を持たなくても良いという利点が出てきます。特に仕事で疲れているという女性には力強い味方になりますので、進んで利用してみるといいでしょう。
家事の優先順位を決める
家事の優先順位を決めるのも、仕事と家事を両立する方法のひとつです。過剰タスクになりがちな妻にとって、すべての家事を完璧にこなすのは現実的ではありません。だからこそ、「何を最優先にするか」をあらかじめ決めておくことが大切です。
例えば、平日は「洗濯と食事の準備だけ」に集中し、掃除は「週末まとめて」行うルールを設定すると、毎日の迷いが減り行動がスムーズになります。
また、「完璧を目指すよりも継続すること」を意識すれば、家事の重圧が軽くなり、ストレスも減少します。外部サービスや家族のサポートを利用するなどを話し合い、メリハリをつけることで妻の家事の負担が減り、仕事と家事の両立がスムーズになります。
両立しやすい仕事への転職を検討する
現在の働き方が家事・育児との両立に合わない場合は、思い切って転職を検討するのもひとつの方法です。例えば在宅勤務を導入すれば通勤時間を削減でき、朝晩の家事負担が軽減し、子どもの送り迎えにも余裕が生まれます。
フレックス制を活用すれば始業・終業時刻を自由に調整できるため、保育園のお迎えや学校行事にも柔軟に対応できるでしょう。転職活動は大変ですが、フルリモートや時短・フレックス制度のある職場を選ぶと、家事と育児の両立がより実現しやすくなります。
制度を活用する
企業や自治体が用意する育児・介護休業、時短勤務、在宅勤務支援、ファミリー・サポート・センターなどの制度が利用できないかを確認しましょう。制度を上手く活用すれば、日々の負担を軽減できる可能性があります。
企業によっては、「育児短時間勤務」を最大3年間まで選べる場合もあります。自治体では学童保育の延長利用やベビーシッター補助、子育て応援券の交付など、経済的支援・保育支援が充実しています。
どの制度が利用できるかは職場の人事担当や自治体窓口で確認し、遠慮せず相談することが仕事と家事を両立する第一歩です。
家事代行サービスに頼る
夫婦共働きである場合は「家事代行サービス」を利用するというのも解決策のひとつです。共働きの強みといえばダブルインカム(収入源が2つ)ということで、シングルインカム(収入源が1つ)よりも経済的に余裕のある家庭が多いと予想されます。
経済的に余裕があるのであれば、日々の掃除や片付け、夫との家事分担に疲れてしまう前に家事代行サービスを使い、外部に頼るという選択肢もあります。家事を任せることでその分の時間が生まれ、心と生活にゆとりが生まれるでしょう。
ちなみに、同じようなサービスではありますが、「ハウスクリーニング」とは少し違います。ハウスクリーニングは、一般家庭ではなかなか掃除できないような部分や落としきれないような汚れを特別な機械や洗剤を使って綺麗にクリーニングしてくれるものです。
家事代行サービスは、普段主婦が行っているような家事を主婦に代わってプロが行うというもので、時間指定で主婦をもう1人雇うようなイメージで考えてもらっていいでしょう。
仕事・家事の両立がしんどい・疲れた時は「ベアーズ」にお任せください

仕事・家事の両立がしんどい時は「ベアーズ」にお任せください。ベアーズは創業20年以上、累計サービス250万件以上の実績を持つ家事代行・ハウスクリーニングサービスです。日常のお掃除、料理、買い物、洗濯などの家事全般を、時間制のオーダーメイドで対応します。
さらに、1~12歳のお子さまを対象にしたベビーシッターサービスも提供しているため、子育てママにもおすすめです。仕事と家事、そして育児の両立に悩んでいる方は、ベアーズに頼ってひと息ついてみませんか?
気になる方は、下記のサイトをチェックしてみてください。
仕事・家事の両立に関するよくある質問

ここからは、仕事・家事の両立に関するよくある質問と回答を紹介します。
・子育てと仕事を両立すると何が大変ですか?
・仕事と家事、どちらが大変ですか?
・仕事と家事のストレスを溜め込まない方法はありますか?
それぞれを詳しく見てみましょう。
子育てと仕事を両立すると何が大変ですか?
子育てと仕事の両立で最も大変なのは、時間に追われる点です。
女の転職typeが2021年5月14日〜5月27日に実施したアンケート調査によると、「仕事と育児の両立で大変なことは?」の質問に対し、「時間に追われる」と回答した人が90.3%と、最も多い結果になりました。
この結果からも、多くの女性が限られた時間のなかで仕事・家事・育児という複数の役割を担い、大きな負担を感じていることがわかります。特に、子どもの急な体調不良や予期せぬ予定変更が重なると、自分のペースが乱れ、心身ともに余裕を失いやすくなります。
時間的なゆとりのなさは、焦りや罪悪感、そしてストレスの蓄積へとつながります。
※参照:女の転職type|Woman type|仕事と育児の両立で女性が最も「大変さ」を感じること第一位は?【アンケート調査】
仕事と家事、どちらが大変ですか?
仕事と家事、どちらが大変かは人によって感じ方が異なりますが、共通して言えるのは「両立が大きな負担になる」という点です。仕事では納期や成果、対人関係などの負担がかかります。
一方、家事は毎日繰り返される終わりのない作業であり、誰にも評価されない場合がはほとんどです。さらに、料理、掃除、洗濯に加え、家族の健康や生活を支える責任も伴います。
どちらか一方だけでも大変なタスクですが、それを同時に担うとなると、心身にかかる負荷は非常に大きくなります。だからこそ、すべてを自分だけで抱え込まず、パートナーや家族と協力したり、便利なサービスや家電を活用したりする工夫が欠かせません。
両立を続けるためにも1人で悩まず、周囲の助けを借りるこもが大切です。
仕事と家事のストレスを溜め込まない方法はありますか?
ストレスをためないためには、休む・手放す・頼るの3つを意識することが大切です。具体的には、家事を1日だけ手抜きにする、ご褒美の時間をあらかじめ決めておく、信頼できるパートナーや家事代行に頼るなどの方法があります。
こうした工夫によって、「自分ばかり頑張っている」という思いから解放され、心にゆとりが生まれます。「がんばりすぎないこと」が、両立を続けるための最大の秘訣と言えるでしょう。
まとめ

仕事と家事の両立は、誰にとっても簡単なことではありません。特に女性は、育児や家事の負担が重なり、限界を感じやすい状況にあります。
しかし、分担の見直しや時短家電の活用、家事代行サービスなど、生活を楽にする方法はたくさんあります。「自分を犠牲にして成り立つ両立」は長続きしません。自分らしく、無理のない形で仕事と家庭を両立するために、今日からできる工夫をひとつずつ取り入れていきましょう。
 Related
-関連記事-
Related
-関連記事-
-

ベアーズの料理代行体験プランを使ってみた正直レビュー|在宅育児がぐっとラクに
ベアーズの料理代行体験プランを、在宅で9ヶ月の子どもを見ながら実際に利用。初回限定プランの内容や当日
ベアーズの料理代行体験プランを、在宅で9ヶ月の子どもを見なが
2026.01.20
-

【体験レビュー】冬休み初日にベアーズのベビーシッター体験プランを使ってみた
ベアーズのベビーシッター体験プランを、業務委託パートナーの筆者が実際に利用。冬休み初日に年少(4歳)
ベアーズのベビーシッター体験プランを、業務委託パートナーの筆
2025.12.29
-

【体験レビュー】おそうじ美人GREENで母へ贈る、エアコンクリーニング体験
家事代行のベアーズが提供するハウスクリーニングギフト「おそうじ美人GREEN」。母へのプレゼントとし
家事代行のベアーズが提供するハウスクリーニングギフト「おそう
2025.10.31
-

【体験レビュー】おそうじ美人RED母の日や妻・義母への感謝を伝える体験型ギフトとは?
「おそうじ美人RED」はベアーズの家事代行ギフト。掃除・洗濯・料理など3時間プロに任せられる体験型プ
「おそうじ美人RED」はベアーズの家事代行ギフト。掃除・洗濯
2025.09.03
-

エアコンクリーニングは効果絶大!メリットや業者選びのポイントを解説
「エアコンクリーニングは必要?どんな効果があるの?」 このような疑問にお答えする記事です。 ...
「エアコンクリーニングは必要?どんな効果があるの?」 この...
2025.06.06
-

【産後の家事代行体験記】二児育児スタートの日に頼ったら大正解だった話
産後の心身の負担を少しでも軽くするために、家事代行と育児サポートを活用してみた30代ママの体験記。産
産後の心身の負担を少しでも軽くするために、家事代行と育児サポ
2025.05.03
![]() Pick Up
-ピックアップ-
Pick Up
-ピックアップ-
-

【体験談】ベアーズの家事代行初回お試しプランは、快適な暮らしへの第一歩
ベアーズの「家事代行初回お試しプラン」の体験談をHさんにインタビュー。共働きで1歳の娘を育てるHさん
ベアーズの「家事代行初回お試しプラン」の体験談をHさんにイン
2023.01.19
-

福利厚生の事例8選|従業員の満足度が高いユニークな福利厚生とは
企業が活動するにあたり、従業員は最も重要な財産といえます。優秀な人材が長く働きやすい環境を築くため...
企業が活動するにあたり、従業員は最も重要な財産といえます。...
2022.12.22
-

冷房の使い始めに注意!エアコン掃除や試運転がポイント!【クリーニングサービス体験談も】
夏への準備、エアコンは試運転した方がいいって本当? 季節は5月。夏はまだ先のこと……と思って...
夏への準備、エアコンは試運転した方がいいって本当? ...
2022.05.09
-

【体験談】子どもと過ごせる時間が増えた!家事代行は自分を大切にするためのサービス
こんにちは、家事代行のベアーズです。 共働き夫婦の中には、「仕事と育児で忙しくて家事まで手が...
こんにちは、家事代行のベアーズです。 共働き夫婦の中...
2022.02.10
-

【体験談】家事代行を頼んで時間と心にゆとりができた!帰宅の瞬間が癒しに
こんにちは、家事代行のベアーズです。 オフィスで働くOさん。ご夫婦で共働き...
こんにちは、家事代行のベアーズです。 ...
2022.01.31
-

ウェルビーイングに貢献する福利厚生とは?社員の生産性を高める5つの例
近年、働く上でのウェルビーイング(幸福感や満足感)の重要性が注目されるようになってきました。従業...
近年、働く上でのウェルビーイング(幸福感や満足感)の重要...
2022.01.07